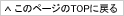2010年度
第30回全国大会 プログラム
| 日時 | 2010年11月7日(日) 10:00~16:00 |
|---|---|
| 場所 | くらしき作陽大学 6号館505 〒710-0292 岡山県倉敷市玉島長尾3515 http://sakuyo.hisc.co.jp/ |
| 交通 | ■JR 山陽新幹線「新倉敷」駅 ■JR 山陽新幹線「岡山」駅→ (山陽本線下り約25分)→「新倉敷」駅 ■岡山空港から リムジンバス約30分→JR「岡山」駅→ (山陽本線下り約25分) →「新倉敷」駅 リムジンバス約25分→JR「倉敷」駅→ (山陽本線下り約10分) →「新倉敷」駅 ※「新倉敷」駅北口より徒歩15分(タクシー利用の場合、乗り場は 北口を出てすぐ) ■山陽自動車道 玉島I.Cをおりて、3分(キャンパス北側に大駐車場 が有ります) |
| 受 付 (9:30~10:00) | ||
| 開会の辞 (10:00) | ||
| 広島市立大学教授 | 土 井 悠 子 | |
| Ⅰ 研究発表(10:00~12:00) | ||
司会 |
広島市立大学教授 | 土 井 悠 子 |
| ヴァージニア・ウルフのチョーサー観――作品への影響 | ||
| 中京大学大学院生 | 中 沢 まゆ子 | |
| E・M・フォースターと二つの世界大戦――ヴァージニア・ウルフとの比較 | ||
| 岡山大学教授 | 剱 持 淑 | |
司会 |
東京学芸大学教授 | 大 田 信 良 |
| ウォレス・スティーヴンスに見られるアメリカ30年代モダニズムの意味 | ||
| 一橋大学大学院生 | 市 川 昭 子 | |
| 文学作品を使用したReading Workshopにおける「誘因と手段」 ―A Room of One’s Ownを使用して― |
||
| 京都外国語大学外国語専門学校主任講師 | 幸 重 美津子 | |
| Ⅱ 総 会(13:10~13:30) | ||
司会 |
帝京大学教授 | 高 井 宏 子 |
| ・会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他 | ||
| 神戸市外国語大学教授 | 御 輿 哲 也 | |
| Ⅲ シンポジウム(13:30~16:00) | ||
| ヴァージニア・ウルフのパーティ空間 | ||
司会・講師 |
大手前大学教授 | 太 田 素 子 |
講師 |
同志社大学教授 | 山 本 妙 |
講師 |
和歌山大学准教授 | 桐 山 恵 子 |
講師 |
相愛大学准教授 | 石 川 玲 子 |
| 閉会の辞(16:00) | ||
会長 |
神戸市外国語大学教授 | 御 輿 哲 也 |
| 懇親会(17:30~20:00) | ||
会場Osteria Pulizia(リットシティビル2F 電話 086-253-4500) 岡山駅西口より徒歩1分 |
||
| 会費6000円(学生 3500円) | ||
研究発表要旨
ヴァージニア・ウルフのチョーサー観―作品への影響
中京大学大学院生 中沢 まゆ子
近年、ウルフと中世の詩人チョーサーの文学的関係を論じる動きがある。ウルフはチョーサーに関し、エッセイ、日記、手紙に記しているのをはじめ、小説中にもそのイメージを用いている。例えば、エッセイ“The Pastons and Chaucer”やBetween the Actsの野外劇のなかのカンタベリー巡礼者が挙げられる。その他、ウルフがチョーサーから受けたであろう影響も作品のなかに多くみられる。ウルフとチョーサーの描写方法は一見、相反するかのようであるが、その意図には共通性が見出せる。ここでは、まず、ウルフの直接的記述からチョーサーに対する捉え方を探り、次に作品への影響を分析する。
E・M・フォースターと二つの世界大戦――ヴァージニア・ウルフとの比較
岡山大学教授 剱持 淑
両大戦中および大戦間のE・M・フォースターの活動と、時代を反映する小説やエッセイをもとに、作家が戦争と戦後にどのように向き合おうとしていたのかを考察する。第一次世界大戦中のエジプトでの国際赤十字の職員としての勤務、インド旅行と滞在(1912-14、1921)を経て書かれた『インドへの道』(1924)、『知恵の七本柱』とT・E・ロレンスとの交友、および第二次世界大戦前・戦中・戦後のエッセイと講演に注目する。フォースターは行動を伴った “pacifist” であった。過去にただ思いをはせるよりも、戦後の困難な世界情勢を想定し、世界の国々の共存と人々の相互理解という難題に立ち向かう必要性と未来の可能性を示そうとした作家であると考える。
ウォレス・スティーヴンスに見られる アメリカ30年代モダニズムの意味
一橋大学大学院生 市川昭子
50年代における30年代モダニズムの評価が、そのラディカリズムを不可視化したことに注意を向ければ、30年代におけるモダニズムの左翼的なものとの交渉が見えてくる。現在もアメリカを代表するモダニスト詩人と評価されるウォレス・スティーブンスの政治的な立場は保守的なハイモダニストとしても、左翼的なモダニストとしても位置付けられない。本発表ではマイケル・ザライが提示する、詩人とニューディールの関係を参照し、後期モダニストとしてのスティーヴンスにおけるニューディールの意味を考察する。
文学作品を使用したReading Workshopにおける「誘因と手段」
―A Room of One’s Ownを使用して―
京都外国語大学外国語専門学校主任講師 幸重 美津子
人は「成功すると期待できるもののみを行なう(Feather, 1982)」という傾向がある。文学作品を使用した英語リーディング指導においても、学習者が読み始めるためには「理解できる」という期待を持たせることが必要(Day, 1998)で、それを持続させるには「誘因と手段」が必要(Harris & Sipay, 1990)だと考えられる。すなわち、学習者に理解可能だと期待させ、読み進めるための誘因としての作業を与えることによって、学習者の積極的な取り組みや興味が維持できると仮定した。本発表では、大学教養課程の学部混合の学生を対象としたReading Workshopにおいて、ヴァージニア・ウルフの作品をテクストとし、Checklistを誘因として使用することにより好結果を得られた授業形態の1例を報告する。
第30回日本ヴァージニア・ウルフ協会大会シンポジウム要旨
ヴァージニア・ウルフのパーティ空間
| 司会・講師 | 大手前大学教授 太田素子 |
| 講師 | 和歌山大学准教授 桐山恵子 |
| 講師 | 相愛大学准教授 石川玲子 |
| 講師 | 同志社大学教授 山本妙 |
パーティをキーワードにして、ヴァージニア・ウルフの作品を読み解こうと試みる。パーティはウルフの作品に於いて重要な役割を果たしていながら、これまで、必ずしも正当に評価されてきたとは言えない。しかし、例えばパーティの催される1日を描く『ダロウェイ夫人』では、「瞬間」を捉える特有の儀式として、パーティが効果的に用いられている。そこでは、もろさと表裏をなしながら至福の「瞬間」が鮮やかに定着されている。
ウルフが、個我や自我に収斂したいわば閉塞的な世界を描いた作家と思われている一面で、常に社会との関係を意識し続けていたことを再考するひとつの試みでもある。パーティ空間を媒介にして、人は社会と幸福に関係を保とうとするが、そうはできない時代や個人の意識のため、様々なアンビヴァレントな意識を感じていると言える。
『ダロウェイ夫人』『灯台へ』『波』をとりあげ、世紀末のオスカー・ワイルドの視点を加えて、山崎正和の「社交論」やC.エイムズのパーティ論を踏まえつつ、ヨーロッパ近代の社交とウルフのパーティ空間について考える。
引きこもる美青年 -『ドリアン・グレイの肖像』における社交-
和歌山大学准教授 桐山恵子
肖像画に老いと罪のしるしを負わせる代わりに、自身は永遠の若さを保つ美貌の青年ドリアン・グレイ。作者オスカー・ワイルドのダンディズムを体現するかのように、最新のファッションに身をつつみ華麗なパーティーに姿を現すドリアンは、輝ける美貌と洗練された物腰で周囲の人々を魅了し続けた。
ところがパーティーの花形であるドリアンには、社交性に富んだ性質とは相反する隠れた一面が見受けられる。一旦、社交の場から離れると、彼は自分ひとりになれる私的な空間を探し求め、しばしそこに引きこもるのだ。もちろん孤高の唯美主義者としてのドリアンを考えると、彼が外部との接触を断った美的空間に引きこもるのは、そう不思議ではないかもしれない。しかし明るい公の場とは対極にある、薄暗い閉所への彼のこだわりは、美を追求する唯美主義実践の範疇を超えているように思われる。
本発表では、社交家としてのドリアンを考察した後、彼が隠しもつ閉所への志向に注目する。単なる唯美小説ではない『ドリアン・グレイの肖像』の新しい解釈を提示してみたい。
ヴィクトリア朝の残光――『灯台へ』のパーティ
相愛大学准教授 石川玲子
『灯台へ』のラムゼイ夫妻にウルフの両親の姿が重ねられていることは、良く知られている。また、ウルフは回想記「過去のスケッチ」の中で、「たくさんの人の集まる、楽しい世界の創り手」としての母亡き後の生活について「二つの違う時代がハイドパーク・ゲイトの居間で対決した」と語り、それがヴィクトリア朝とエドワード朝であると説明している。このようなことを考えると、戦前の一日を描く『灯台へ』第一章のパーティは、ウルフにとって生前の母が作り上げた調和的世界を具現するものであり、いわば、父母の世代が属するヴィクトリア朝の煌めきをテクストの中に留めたものとして見ることができるのではないだろうか。
本発表では、『灯台へ』のパーティを議論の中心に据えて、夫人の社交のあり方、そこにみられる社会と個人の関係性を、夫人自身の視点と、パーティに半ば加担しつつも反発を禁じえないリリーのアンビヴァレントな視座の両方から考える。そしてそこに、ヴィクトリア朝時代に向けられたウルフ自身のまなざしを見いだしたい。
『波』におけるパーティ空間の変容
同志社大学教授 山本妙
『波』におけるパーティ空間ときいて頭に浮かぶのは、パーシヴァルの壮行会と、ハンプトン・コートの会合だが、これらの集まりは、前二作におけるパーティのような力をもたないように見える。理由として、この作品では、自我なき薄暮の次元へ沈潜しようとする志向と、それに抗して活動しようとする志向との振り子運動を繰り返したあげく、最終章のバーナードの独白において「自我なしに見られた世界」が現出するまでを描くことに主眼をおいているため、両者の幸福なバランスに焦点をあてることがもはやなくなった、ということがあげられよう。前二作とは異なり、『波』では大戦への言及によってパーティの時期がわかる、ということがないのも、生の普遍的な相貌を描く作品にしたいという意図の表れとも読める。しかし、「インドに赴いた」パーシヴァルの悲報に接して音楽を聴き、「構造を看取する」ローダや、ナショナル・ギャラリーで絵画を鑑賞して彼を弔うバーナードの経験は、明らかに20世紀を折り返してから後のものである。ラムゼイ夫人やダロウェイ夫人のパーティはもう開かれ得ず、代わりにあるのは、このような個々人の、「文化」と「外界」との接触なのだという認識が、このようなところに見てとれるのではないだろうか。執筆された「時」を念頭におきながら、パーティが「なぜ」「どう」変わったかを考えてみたい。