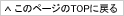2021年度
2021年11月7日(日)開催予定の第 41 回全国大会につきましては、昨年に引き続きオンライン開催いたします。セキュリティ等への配慮から、参加は事前登録制となっております。
* 会員の方々は9月20日発行のニューズレターをご参照のうえ、10月8日(金)~10月24 日(日)の間に参加申請をお願いいたします。
* 非会員の方々のご参加も歓迎いたします。参加を希望される方は、件名に「大会参加希望」と明記し、10月27日(水)までに事務局(vwoolfsocietyjpn@gmail.com)にご連絡の上、29日(金)までに指定した協会の銀行口座に当日会費 500 円をお振込みいただくようお願いいたします。振込後に、こちらからお送りするURLで事前参加登録を済ませてください(10月8日以降にお知らせいたします)。
事前参加登録後は、会費の納入と事前参加登録の登録内容の確認がとれましたら大会委員が参加を承認し、当日の大会参加のための招待メールをお送りします。当日はメールに記載の「ミーティングに参加」をクリックするか、URLをブラウザに張り付けてご参加ください。
11月2日(火)までにこのメールが送信されなかった場合は、事務局にご連絡ください。
研究発表・シンポジウム・ラウンドテーブルの要旨は以下の通りです。
「ヴァージニア・ウルフの『船出』における⾃⼰消去と原光景」
広島⼤学⼤学院⽣ 松崎 翔⽃
『船出』はヴァージニア・ウルフが初めて書いた⻑編⼩説で、レイチェルの成⻑を描いた教養⼩説である。本発表において私が着⽬するのは、この作品における⾃⼰を他者の視線から消してしまう⾏為、すなわち⾃⼰消去とでもいうべきものである。例えば、登場⼈物たちの覗き⾒や盗み聞きが⾃⼰消去の例として挙げられる。加えて、レイチェルのピアノを弾く⾏為やヒューエットの物事を書く⾏為に対する考え⽅においても⾃⼰消去は確認できる。
具体的に覗き⾒として挙げられるものには、‘seeing life’ を合⾔葉にレイチェルとヘレンがテレンスの滞在するホテルを覗き⾒たこと(と同時にスン・ジョンに盗み⾒られていたこと)や、モンテ・ローザへのハイキングの際にレイチェルとテレンスがスーザンとアーサーが愛し合う光景(性⾏為らしき光景)を不意に陰から⾒てしまったことなどがある。とりわけ興味深いのは、初めて覗き⾒が⾏われた場所が鶏の屠殺場であったことである。もし、スーザンとアーサーの愛し合う光景を原光景と⾔うことができるならば、レイチェルが熱病に苦しみつつ⾒る幻覚に表れるように、この鶏の屠殺は何か特別な意味を持つのではないだろうか。⼀⽅、盗み聞きとして例に挙げることができるのは、ヒューエットのレイチェルとヘレンがいる部屋の盗み聞きである。そして、⾃⼰を消去して何かを⾒るあるいは聞くといった考えは、ヒューエットの⼩説を書くという⾏為における ‘one wants merely to be allowed to see them [things]’ という態度に昇華されており、これはレイチェルのものの考え⽅やピアノを弾く⾏為にもみられるものだ。
本発表では、『船出』にみられる以上のような「⾃⼰消去」――「覗き⾒」、「盗み聞き」、「書く」⾏為、「弾く」⾏為――を登場⼈物が⾏う意味を考察したい。また、初めて「覗き⾒」が⾏われた場所が鶏の屠殺場であるという事実とスーザンとアーサーの性⾏為らしき光景の⽬撃との関係にも注⽬したい。
シンポジウム要旨
1. 「みんなの21世紀ウルフ研究——コスモポリタニズム・建築・緊縮ノスタルジア」
| 司会・講師 | ⼤東⽂化⼤学准教授 | 菊池 かおり |
| 講師 | 名古屋外国語⼤学専任講師 | 中⼟井 智 |
| 講師 | 成城⼤学教授 | ⽊下 誠 |
2000年頃からみられるモダニズム研究の急速な「拡張」は、研究対象に対する「時間的」「空間的」「縦断的」な視点の「拡張」であるのならば、それは、冷戦期に制度化され、幅広く享受された狭義なモダニズムのイデオロギーからの脱却であり、広義に解釈するのならば、⽶国中⼼主義からの脱却とも⾔えるかもしれない。このような状況下において、それまでモダニズムのカノンとして取り扱われることの多かったヴァージニア・ウルフの作品は、新たな⽂脈での再読・再評価が進み、その解釈は、より「学際性」が⾊濃くなると同時に細分化され、専⾨性をともなう傾向にある。それは、ウルフのみならず、同時代の他の作家についても同様のことが⾔えるだろう。そのため、本シンポジウムでは、2000年代以降のモダニズム研究の「拡張」と「学際性」を念頭におきつつ、⾝体・空間・建築という視点を起点として、ウルフ研究の動向を確認しつつ、新モダニズム研究(new modernist studies)、メディア・テクノロジー論、さらにはグローバリゼーション/コスモポリタニズム論の位置づけや、今後の展開やその意義を考えてみたい。(菊池 かおり)
“Enfolding Feminism”を再考する
中⼟井智
1970年代より「⾝体」は⼈間の想像⼒を統制する為の規制対象として議論され始めた。この前提に基づき、2000年代以降ウルフのテクストには、階級やジェンダー規範が社会的⾝体に課す制限を⾔葉によって克服し、異なる習慣を持つ者同⼠が想像により連帯する可能性が検討されてきた。グローバリゼーション/コスモポリタニズム論の観点から、Jessica Berman, Modernist Fiction, Cosmopolitanism and the Politics of Community (2001)やModernist Commitments: Ethics, Politics, and Transnational Modernism (2011)は、Mieke Balがフェミニズムのコンセプトを⽰した“Enfolding Feminism” (Bal 2001)にて主体と客体の分離を解消する概念として提案した“fold”の効果を、『ダロウェイ夫⼈』の「カーテン」や『灯台へ』の「⼿袋」の⽐喩などに応⽤し、例えばクラリッサが向かいの⾒知らぬお婆さんを気遣い、倫理的な関係を想像する際の媒介であると解釈する(Berman2011)。本シンポジウムでは、“Enfolding Feminism”を「⾝体」の意味を中⼼に再確認することでバーマンがバルから借⽤した“fold”の解釈の妥当性と、審美的な解釈が潜在化させる階級の問題を考える。
建築に夢⾒たモダニズム
菊池 かおり
ヴァージニア・ウルフを含めたモダニスト作家の空間描写が含蓄する重層的な歴史性や政治性は、2000年代以降、様々な視点から論じられてきたが、その空間描写と密接にかかわる建築という視点からのモダニズム論は、まだ限定的であるように思われる。例えば、ル・コルビュジェを筆頭とするdominantなモダニズム建築・モダナイゼーションとそれに対してsubversiveなモダニズム⽂学という図式で論じられる傾向にある。⼀⽅で、2020年に刊⾏されたAshley Maher, Reconstructing Modernism: British Literature, Modern Architecture, and the Stateは、近年、隆盛を極める学際的なモダニズム研究において⾒過ごされてきた建築と⽂学の関係性に着⽬し、モダニスト作家による建築批評を読み解くことで、モダニズム⽂学への影響について論じている。本発表では、空間と建築をテーマとした近年のモダニズム論とウルフ研究の動向を概観しつつ、そこから浮かび上がる戦間期イギリスにおける建築と⽂学の関係性、そしてその関係性に対するアプローチにみられる傾向を考察し、今後のウルフ研究の可能性を模索してみたい。
“Keep Calm & Carry On”——「緊縮ノスタルジア」と内向きのモダニズム研究
⽊下 誠
Owen Hatherley, The Ministry of Nostalgia (2016, オーウェン・ハサリー『緊縮ノスタルジア』星野真志・⽥尻歩[訳]堀之内出版 2021年)によれば、1910年代後半のヨーロッパ⼤陸では、多様な政治的および美的形態をとってブルジョワの価値観に反旗を翻したアヴァンギャルド運動が「優雅に合理化された産業デザインと芸術と建築を国家に奉仕させるという計画のもとに集結」した。しかし同時期のイギリスでは、「1908年前後のパリの美的趣向というゼリーを氷漬け」したブルームズベリー・グループの美的趣向が「近代性の頂点」と考えられていたために、⼤陸と同様の動きへと結実することはなかった、という。ウルフ研究者ではない⽴場で本シンポジウムに参加する者として、まずはこうした図式の妥当性を議論したいと思う。かつてアヴァンギャルド運動が内包していたはずのユートピア・ヴィジョンは、戦後冷戦期にディストピアへと読み替えられ、私たちのモダニズム⽂学理解のある部分を規定してしまったのではないだろうか。そして結局のところ、「1910年の12⽉かそのあたり」にイギリスを⼤きく変えるきっかけを作ったのかもしれないブルームズベリー・グループの「先進性」は、その「先進性」を包み込んだ「1908年頃のパリの美的趣向というゼリー」が解凍された結果、2000年代に⼊って興隆したモダニズム⽂学とイングリッシュネスの関係あるいはプライヴェート空間の再検討をめぐる研究、いわゆる内向きのモダニズム研究へと引き継がれたのではないだろうか。
2.「Bright Young Things の/とモダニズム」
| 司会・講師 | 福島⼤学教授 | 髙⽥ 英和 |
| 講師 | ⻘⼭学院⼤学教授 | ⼤道 千穂 |
| 講師 | ⼀橋⼤学教授 | 井川 ちとせ |
本シンポジウムは、英国モダニズム⽂学研究において軽視されがちであった、同時代の上流階級に焦点をあてる。20世紀初頭の1920年代は⽂学史上においてはいわゆるハイ・モダニズムの時代だが、前世紀末ごろから登場し、その種類や発⾏部数を急速にのばした、⼀般⼤衆向けのタブロイド紙が興隆した時期でもあった。こうしたタブロイド紙をおおいににぎわせたのが、Bright Young Thingsと⼤衆メディアに名付けられた、上流階級の⼀部の若者たちであった。⽇夜を問わず派⼿なパーティーや⼤掛かりなゲームや悪ふざけに興じるBright Young Thingsの快楽主義的で退廃的な⽂化とモダニズム芸術の接点は、従来のいわゆる真正の「英⽂学」研究においては、⼗分には議論されてはこなかったのではないか。たとえば、T. S. EliotからF. R. Leavisまでの仕事から離反した道を歩いたMartin Greenの⽂化史的・「⽂化⼼理学的」な研究――Raymond Williams の批判的継承・修正とは別に――にはじまり、近年までさまざまに実践される⽂化研究・⽂化史の仕事はいくらでもあるし、ある意味英国的な狭義のモダニズム⽂学研究で断⽚的・部分的に都合よく⾔及されたり踏み台にされたりすることはあるとしても、である。
しかし実は、「衰退」していく⼤英帝国の中枢で活躍した親たちの旧来の価値観や⽣活様式などすべてに反抗した彼ら/彼⼥らと、それまでの英国⼩説の在り⽅に異を唱えて勃興したモダニズム⽂学は、互いに相容れないものとはいえない。両者は、17世紀にはじまるヨーロッパを起点としたモダニティの⼤衆化という歴史的可能性の条件を共有し、英国の⽂学・⽂化空間において共存し対⽴しつつも交錯していたのではないか。戦間期英国のナショナルな⽂化とは対照的なコスモポリタンなハイ・モダニズムもまた、たとえば、ヴァージニア・ウルフのそれがそうであるように、1920年代に最盛期を迎え、その後は、なんとなく、ぼんやりと下⽕に向かっていったようであるが、このことは、上記のBright Young Thingsの⽂化と、関連していないのだろうか。というのも、モダニズム(特にブルームズベリー・グループのそれ)が、⾼尚であったこと、と同時に、⽣/性に対して奔放であったこと、さらには、レイト・モダニズムというかたち・すがたで存続・延命していたこと、を鑑みれば、モダニズムとこの若者たちの⽂化とのあいだには、なにがしかの、ひょっとすると密接な、関係があるかもしれないし、⼀度は、考えてみるのも良いかもしれない。
パブリックスクール出⾝の知的貴族階級の男性たちとそれを取り巻く⼥性たちが、ハイ・モダニズムの時代に何を思い、どのように⽣きたか、ということを「リ・デザイン」することで、モダニティの⼤衆化がさらにグローバル化した21 世紀のいま、英国モダニズムの⽂学および⽂化をより幅広くトータルにとらえ、読み直すことを本シンポジウムは試みるものである。(髙⽥英和)
Bright Young Things とその時代――王室、上流階級の戦間期
⼤道 千穂
本報告では、まず、Bright Young Thingsとは何者なのか、なぜパブリックスクール出⾝の知的エリートたちがこのような存在になったのかということを、時代性とからめて読み解いていきたい。Bright Young Thingsという名がメディアにつけられたものであることが端的に⽰すように、彼らの存在は⼤衆化したメディアの存在なしにはありえない。そして、彼らにとっての英雄であったプリンス・オブ・ウェールズ(後のエドワード⼋世)もまた、メディアとの親和性が⾼かった。王室の伝統と格式に強いこだわりを持ち、⼤衆との⼀定の距離間にも意識的であった⽗ジョージ五世に反抗したエドワード⼋世も、Bright Young Things同様、旧来の価値観から放たれて新たな道を進もうした⼀⼈と⾔える。
Bright Young Thingsもエドワード⼋世も、特に⽂学研究においては歴史の中の例外的な存在として⽚づけられてしまう傾向があり、あまり注⽬されることがなかった。しかし、彼らはモダニズムの作家たちと同じ時代を共有し、そして作家の階級によっては互いに交流も持っていた。抹殺された Bright Young Thingsを歴史の中に戻すことで、モダニズム⽂学を考える地平は広がるのではないだろうか。このような視点で、モダニズム時代の王室、上流階級の⽂化や葛藤を探ってみたい。
“Bright Young Things/People”の⻩昏?
ーー戦間期および世紀半ば(Mid-century)の英国のリベラリズムと児童⽂学
髙⽥ 英和
1920年代初めの英国に出現した、新しい若いグループ・集団を“Bright Young People”といい、そして、その彼ら/彼⼥らの⽂化を、総じて、“Bright Young Things”ということは、周知のことであるし、その特徴を、⼀⾔で述べるのなら、それは、「貴族的」且つまたセレブ的、であるということも、広く知れ渡っていることだろう。ここで、おもしろいのは、「貴族的」・セレブ的とは⾔っても、この若者たちには、お淑やかさは微塵もなく、⼤量の飲酒をするわ、⿇薬も嗜んだりと、朝⽅までどんちゃん騒ぎの「パリピ」の毎⽇という感じで、ある意味、そこには、⼤衆・消費⽂化の醍醐味とその雰囲気が、⾔い換えれば、ハイ・カルチャーとは対照的なポピュラー・カルチャーが、これでもかと⾔うほど全⾯に押し出されていて、それゆえに、この点にこそ、この若者たちの⽂化のおもしろみや歴史的意味があるのかもしれない。この“Bright Young Things”の⽂化は、1920年代の末には、衰退するとされているようなのだが、はたして、そうなのか。
本発表では、“Bright Young Things/People”がその勢いを失ったと⾔われるあとの時代、すなわち、1930年代の英国の社会/⽂化を、(でもこの若者⽂化の残滓を頭に⼊れながら)今⼀度、だが批判的に、⾒ていくことにする。具体的には、1)オックスフォードの「インクリングズ(Inklings)」の系譜に連なるあるいは深層で関係すると思しき作家や⼈物およびその作品(群)すなわち⽂藝・⽂壇とその⽂化、そして、2)英国の都会の暮らしや⽣活とその様式というよりは、むしろ、農村の社会と⽂化、これら⼆点に着⽬する。そのうえで、“BrightYoung Thing/People”の影または亡霊というようなものが、どのように、30年代の(さらには50年代・Mid-centuryをも視野に⼊れながら)オックスフォードを中⼼とするファンタジー・児童⽂学および⽥舎性を纏う/纏い続ける英国のリベラリズムの⽂化と、絡まっているのかを探ってみたい。
フィーメール・ダンディ・アットホームズ――⼤戦間期の英国サロン⽂化
井川 ちとせ
Martin GreenはChildren of the Sun: A Narrative of “Decadence” in England after 1918 (1976)で、1901年からの10年間に⽣まれた世代が牽引した⽂化について論じている。責任ある家⻑になることを拒んだ「太陽の⼦たち」のなかでも最も⼤きな影響⼒を誇ったHarold ActonとBrian Howardという2⼈のダンディを中⼼に据えながら、Greenは脚注で、⼥もダンディ⾜り得ると付⾔、Nancy Mitford, Virginia Woolf, Edith Sitwellの名を挙げている。彼ら/彼⼥らのネットワークを後づけるGreenの⼿際は鮮やかではあるが、イートン校、オックスフォード⼤学、ロンドン、カントリーハウスを主要な舞台に、上流階級の排他性とエディプス的な世代間闘争を強調し過ぎる嫌いがあるように思われる。本報告では、Edith Sitwellの粗末なフラットでのサロンやthe Anglo-French Societyでの活動などに光を当て、フィーメール・ダンディの系譜を記述する可能性を探りたい。
ラウンドテーブル要旨
「ウルフとコモンリーダー」
| 司会 | 都留⽂科⼤学教授 | 加藤 めぐみ |
| 講師 | 上智⼤学教授 | ⼩川 公代 |
| 講師 | 翻訳家・エッセイスト | 鴻巣 友季⼦ |
| 講師 | 詩⼈・翻訳家 | 森⼭ 恵 |
2021 年現在、⽇本でちょっとしたヴァージニア・ウルフのブームが巻き起こっている。ここ数年、新訳が続々と出版され、ウルフにオマージュを捧げた作品を⽇本の現代作家が相次いで発表、そして今年3⽉にはウルフを「ユーモアもたっぷりで親しみやすい」と紹介し、同⼈誌として1000 部を完売した⼩澤みゆき編『かわいいウルフ』が単⾏本化された。海外ではウルフの影響が舞台芸術やファッションにも及び、『オルランドー』はオペラやバレエに翻案され、バーバリー、フェンディなどの⾼級ブランドも、この作品から着想を得たコレクションを発表している。
なぜいま、ウルフの⽣き⽅、作品が21 世紀を⽣きる我々の⼼に響くのか。――本企画では、⽂学を研究する⽴場にはない⼀般の読者、いわゆるコモンリーダーの間でウルフの受容が⾼まっている最近の動向をご紹介するとともに、ウルフの⽂学や思想が、現代社会で求められている背景について「ラウンドテーブル(⿍談)」という形で探っていきたい。
そこで講師として⽂芸、評論、翻訳など、さまざまな形でウルフ⽂学をコモンリーダーに拓き、現在のウルフブームの⽕付け役のお役⽬を果たされている三⼈の先⽣をお迎えする。上智⼤学教授の⼩川公代⽒は2018年英語劇『オーランドー(王蘭道)』の脚本、演出を⼿掛けられ、8⽉末に出版された最新刊『ケアの論理とエンパワメント』(講談社)では、⾃⼰と他者の関係性としての〈ケア〉の観点からウルフなどの⽂学作品を読み解き、話題をよんでいる。翻訳家、⽂芸評論家の鴻巣友季⼦⽒は『灯台へ』(河出書房新社)の新訳を2009年に発表され、『群像』『朝⽇新聞』をはじめとする⽂芸批評の世界でウルフ⽂学の魅⼒、国内外の現代⽂学、社会への影響などについて広く発信してこられた。そして詩⼈、翻訳家の森⼭恵⽒は今年6 ⽉に45 年ぶりとなる『波』(早川書房)の新訳を出版され、『群像』11⽉号には新たなウルフ論をご執筆予定である。
まずは三⼈の先⽣⽅から、これまでのウルフとの関わり、ご関⼼、お仕事について、それぞれ10 分程度お話をいただき、そのうえで「⿍談」として、2021年の今、コモンリーダーがウルフを読むこと、その魅⼒、翻訳(翻案)の意義など、⾃由にご議論いただく。最後の質疑応答の時間は少し⻑めに設定して、フロアにひらくため、ウルフ協会の会員とコモンリーダーとの⾃由な意⾒交換、さらなる闊達な議論が展開することと期待される。(加藤めぐみ)
*なおラウンドテーブル「ウルフとコモンリーダー」の⿍談については、講談社『群像』の2022年新年号(2021年12 ⽉発売)に掲載予定です。そのため録画、録⾳をいたしますことをあらかじめご承知おきください。