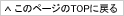2016年度
第36回全国大会 プログラム
| 日時 | 2016年10月29日(土)10:00~17:20 |
|---|---|
| 場所 | 京都女子大学 J校舎5階 J525教室 〒605-8501 京都市東山区今熊野北日吉町35 |
| 交通 | ■ JR、近鉄京都駅よりバス、タクシーで10分 ■ 阪急河原町駅よりバス、タクシーで10分 *どちらの駅からも大学への直通バス「プリンセス・ライン」がご利用いただけます。 大学ホームページから「交通アクセス」をご覧ください。 ■ 京阪七条駅より徒歩15分 |
| 受 付(9:30~10:00) | ||
| 開会の辞 (10:00) | ||
| 成蹊大学教授 | 遠 藤 不 比 人 | |
| Ⅰ 研 究 発 表(10:00~11:40) | ||
司会 |
青山学院大学准教授 | 秦 邦 生 |
| To the Lighthouseにおける美学と歴史――Lily Briscoeの形式主義 | ||
| 東北大学大学院生 | 酒 井 祐 輔 | |
| 『インドへの道』とヘリテージ映画におけるイングリッシュネス | ||
| 早稲田大学非常勤講師 | 岩 崎 雅 之 | |
司会 |
青山学院大学教授 | 麻 生 え り か |
| ヴェラ・ブリテンのTestament of Youth (1933)における自伝の効用 | ||
| 一橋大学大学院生 | 甲 斐 絵 理 | |
| Ⅱ 総 会(13:00~13:20) | ||
司会 |
成蹊大学教授 | 遠 藤 不 比 人 |
| 会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他 | ||
| 大手前大学教授 | 太 田 素 子 | |
| Ⅳ シンポジウム(13:30~16:00) | ||
| 曖昧さの魅力――モダニズム期の女性作家たち | ||
司会 |
神戸市外国語大学教授 | 御 輿 哲 也 |
講師 |
ノートルダム清心女子大学講師 | 松 井 か や |
講師 |
神戸大学准教授 | 奥 村 沙 矢 香 |
講師 |
相愛大学准教授 | 石 川 玲 子 |
| 特別講演 (16:15~17:15) | ||
司会 |
都留文科大学准教授 | 加 藤 め ぐ み |
| 『幕間』における田園主義的イングリッシュネス――ナショナリズムと戦争 | ||
| 法政大学教授 | 丹 治 愛 | |
| 閉会の辞 (17:15) | ||
会長 |
大手前大学教授 | 太 田 素 子 |
| 懇 親 会 (18:00~20:20) | ||
会場ホテルグランヴィア京都(JR京都駅直結)15階 スカイラウンジ「サザンコート」 |
||
| 会費6000円(学生3500円) | ||
| 〒180-8633 武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 成蹊大学文学部 遠藤不比人研究室 日本ヴァージニア・ウルフ協会事務局 |
||
|
〔昼食について〕 会場近辺にはレストランや店舗はほとんどございませんので、あらかじめご用意いただくか、大学内の各種学食(最寄りのものは会場から2分ほどの距離にあるベーカリーカフェ)をご利用くださいませ。 [大会・懇親会への出欠確認の方法について] 昨年同様に、協会HPの新着情報に「2016年全国大会出欠連絡のサイト」を設けました。そこをクリックいただき、サイトにアクセス、ご氏名、電子メールアドレスをご記入の後に、大会、総会、懇親会にご出席になる場合は該当箇所を選択いただき、「送信」という箇所をクリックいただくだけのお手間です。恐縮ながら、10月1日(土)までにお返事を頂戴できれば幸いです。(回答後に変更が生じた場合、同じフォームで再度ご回答ください。) |
研究発表・シンポジウム・特別講演要旨
研究発表要旨
To the Lighthouseにおける美学と歴史――Lily Briscoeの形式主義
東北大学大学院生 酒井祐輔
Virginia Woolfと美学の関係についての過去の研究は、以下の二つの傾向、すなわち、Roger FryやClive Bell、Venessa Bellといった画家・美術評論家からの影響を論じるものと、Woolfの作品と当時の社会情勢との関わりを分析しようとするものに大別できる。後者の批評は、Woolfのエッセイや三〇 年代以降の後期作品を中心に論じることが多いのに対し、前者の批評において特権的な位置を占めてきたのが、作中の重要人物の一人に画家のLily Briscoeを含む小説To the Lighthouse (1927)であった。
Woolfの作品と同時代の絵画理論との関連についての研究の中でも代表的なものとしては、Alllen McLaurinによる七〇年代の研究と、Jane Goldmanによる九〇年代末の研究の二つが挙げられる。Fryの形式主義美学がWoolfに与えた影響を論じたMcLaurinに対し、GoldmanはWoolfの美学を当時のサフラジスト運動の文脈と接続することを試みた。審美的関心から政治的批評へ、というウルフ研究の転回を象徴するともいえるGoldmanの研究はしかし、作品の精読は非政治的であり、文化研究的アプローチは政治的であるという批評における通俗的認識を不必要に反復してしまった部分があるのではないか。
本発表においては、To the Lighthouseの精読を通してWoolf作品に見られる形式主義美学は必ずしも政治からの逃避や置き換えではなく、むしろその中にこそ、Woolfの文学テクストの政治性が託されていたのだと論じる。三〇年代の社会情勢との関連でOrlandoやThe Wavesを論じたJessica Berman は、Woolfが提示しようとしていた共同体観はアトム的な個人主義とも一枚岩的な集団主義とも異なるモザイク的なものであったと主張した。こうした共同体観と併せて考察できるかもしれないのが、Mrs. DallowayやTo the Lighthouseにおける、複数の作中人物の意識を自由に出入りする「全知の」語りであろう。実際、Michael LevensonはTo the Lighthouse第一部の一節を取り上げて、全知の語りが作中人物たちの孤独な意識を回収することで逆説的にも共同体感覚を創出するのだと論じている。
Levensonによる分析が示唆するのは、Bermanが論じたようなWoolfの共同体提示の試みは、二〇年代のテクストにおいて、形式的実験としてすでに始まっていたのかもしれないということだ。ここからWoolf作品の形式主義美学そのものを歴史化する途が拓けるはずである。この分析をさらに精緻化すべく、本発表では、Lilyの絵画制作および他の登場人物との関係の描かれ方に注目して、上述したようなWoolfの共同体観において、芸術・あるいは芸術家がどのような役割を担うことになるのかを検討したい。作品内において芸術とそれに関わる活動がどう位置づけられているかを分析することで、Woolfが自らの創作をいかにして同時代の社会情勢の中に組み入れようとしていたのかについて考える手がかりが得られるだろう。
本発表において取り上げたい箇所のひとつとして、第三部 “The Lighthouse” でLilyがかつて海辺で過ごした時のことを回想する段落がある。ジェネラル・ストライキの勃発を見た小説執筆当時の歴史的文脈において理解するならば、中・上流階級的な秩序を代表するMrs. Ramsayと下層中流・労働者階級的な背景の濃いTansleyが共生しているこの一節はユートピア的なビジョンに他ならない。Lilyは社会から孤絶した芸術家像を前提とする形式主義的・観照的美学と、より直接的に理想的共同体を提示しようとする欲求とに引き裂かれているのであって、これは当時のWoolf自身の状況とも重なってくる。WoolfはLilyの姿を通して、自分が依拠する美学の可能性と限界――つまるところ、芸術とはなにかという宿命的な問い――を問い直そうとしているのである。
本発表では、九〇年代以降の新歴史主義的・文化研究的な研究の成果を活かしてWoolf作品を歴史的地平の中に位置づけつつ、もう一度その形式的特性に研究の焦点を向け直すことを試みてみたい。
Works Cited
Berman, Jessica. Modernist Fiction, Cosmopolitanism and the Politics of Community. Cambridge: Cambridge UP, 2007. Print.
Goldman, Jane. The Feminist Aesthetics of Virginia Woolf. Cambridge: Cambridge UP, 1998. Print.
McLaurin, Allen. Virginia Woolf: The Echoes Enslaved. 1973. Cambridge: Cambridge UP, 2010. Print.
Levenson, Michael. “Narrative Perspective in To the Lighthouse.” The Cambridge Companion to To the Lighthouse. Ed. Allison Peace. New York: Cambridge UP, 2015. 19-29. Print.
『インドへの道』とヘリテージ映画におけるイングリッシュネス
早稲田大学非常勤講師 岩崎雅之
本発表では、E. M. ForsterのA Passage to India (1924) におけるナラティヴと、1984年にDavid Leanによって映像化された映画のナラティヴの比較を行うことを目的とする。具体的には、のちにHeritage filmと呼ばれることになったLeanの映像作品が、帝国主義的男性性の衰退を表象する原作の、どのような側面をイギリスが過去から受け継ぐべきイングリッシュネスとして受容しているのかを、現代のアイデンティティ・ポリティクスとの関連で前景化されることになった、Adela Questedの扱い方に注目して分析するものである。
昨今のイングリッシュネス研究で論じられている通り、A Passage to Indiaには1920年代における大英帝国の衰退が読み取れる。第一次世界大戦の疲弊から立ち直れずにいたイギリスは、アイルランド自治の独立、ガンジーを中心としたインドの独立運動、アフリカにおける労働者たちのストなどを経験し、帝国内外における影響力を失った。その衰退を決定付けたのが、カルカッタからデリーへのインドの首都の移転であった。1857年の反乱の再発を恐れたイギリス人たちは、カルカッタのベンガル人地区がますます不安定になったために、逃げ出すようにしてデリーへと移った。
このような帝国の影響力の衰退によって、帝国主義的男性像も大きな変容を被った。例えばそれは、1857年のインドの反乱の再発に怯えるRonny Heaslopの心理を通じて明らかにされているように、インドにおけるイギリス人紳士像の解体、すなわち帝国主義的男性性の衰退として現れるものだった。Heaslopは、インドにおける正義の執行を建前とし、男性同士の絆によって植民地のイギリス人女性を守るという騎士道精神を発揮しようとし、彼は婚約者であるAdelaと母親であるMrs Mooreに現地のインド人と親密になることを禁ずる。しかし、帝国主義的男性性を否定するFieldingは、Heaslopをはじめとしたアングロ・インディアンたちが作り上げ、守ろうとしているホモソーシャルな帝国の絆を破壊する。クラブの女性たちは、本国では時代遅れとなっている男性の騎士道精神によってもてなされることを求めるが、Fieldingはそのような要望には応えず、友人であるAzizや他のインド人たちとの関係を優先し、そのため彼の特殊な男性性は、英国人紳士像の理想像を脱-人種化し、解体していくことになる。
このように、原作では帝国の衰退によって引き起こされた帝国主義的男性性の衰退および解体が見られるが、David Leanは1980年代のサッチャー政権下において、A Passage to Indiaを翻案し、現代のイギリス国民が求めていた過去の強きイギリスのイメージをHeritage filmとして提示した。原作からの大きな変更点として、Fielding とAzizの関係ではなく、Adelaをめぐるセクシュアリティの問題が前景化されているということが挙げられるが、FieldingとAzizの同性愛的問題を回避して継承されるイングリッシュネスとはどのようなものなのだろうか。先行研究ではまだ論じられていない大英帝国の衰退とHeritage filmの関係を探りたい。
ヴェラ・ブリテンのTestament of Youthにおける自伝の効用
一橋大学大学院生 甲斐絵理
ヴェラ・ブリテン (Vera Brittain: 1893-1970) は、第一次世界大戦においてV.A.D.(救急看護奉仕隊)としてイギリス・フランスなどで看護活動した。その間に、従軍した婚約者ローランド・レイトン (Roland Leighton: 1895-1915)、親友ビクター・リチャードソン (Victor Richardson: 1895-1917)、そして弟エドワード・ブリテン (Edward Brittain: 1895-1918)を次々に戦場で亡くし、その経験をもとに彼女は自伝Testament of Youth (1933)を書いた。ブリテンは自伝という形式に強い関心を抱いており、それはこの作品の後さらに自伝を2冊書いたこと、ロバート・グレイブス (Robert Graves: 1895-1985)やエドマンド・ブランデン (Edmund Blunden: 1896-1974)の自伝の研究をし、ジョン・バニヤン (John Bunyan: 1628-1688)の自伝については研究書を出版している点からもわかる。本論では、女性が戦争を「自伝」という形式で書いたことに注目する。戦中から戦前にかけての女性と戦争の関わりを考察し、女性が自伝という形式で戦争を書くことの社会的な意味について考える。
ブリテンのV.A.D.としての戦争への従軍は、「身代わりの (Vicarious) 精神」から生まれた。それは、戦場で自分が厳しい環境に耐え献身して働くことで、戦争に行った男たちの命を救うことになるというキリスト教的思想に起因する。しかしブリテンの愛する男たちは戦死した。戦後の大学で再会した学長は彼女に冷たい態度をとり、英国王女には「戦争は楽しめましたか?」と問われている。つまり、銃後の市民が思う戦争の英雄像や戦争観と、戦争に従軍した若者の戦争観とのあいだには大きなずれがあった。戦前の男たちの詩や語りにおいても死は冒険や名誉として書き換えられ、その悲しみや恐怖を語ることは困難だった。
そのような男たちの本心はしばしば、女性に向けて書かれた言葉の中にあったようである。戦争に行った男たちの手紙や日記の引用は、ブリテンの自伝の形式の特徴である。男たちの感情的な本音、語れることの難しかった声は、女性に向けた言葉の中において現れた。この作品に登場する男たちは皆、第一次世界大戦時に戦場で亡くなったために、死が書き換えられる男たちの語りの中では彼らの存在は抑圧される。しかしブリテンは彼らの手紙や彼らの思い出を書いた日記を数多くそのままのかたちで引用することによって、彼らの声を記録し再生することに成功している。またブリテンは当初は彼女の戦争体験を小説として再生しようとしていたが、その小説すべてに共通して「子ども」が登場する。ブリテンは第二子妊娠中にこの自伝を書いたが、それは亡くなった男たちの抑圧された声に命を与えることを意味するのである。
第一次世界大戦後、ある若い男が、ブリテンが「自伝を書いています」と言ったことに対し、あなたの人生に記録するほどの価値はないという発言したというエピソードは、当時の女性が自伝を書くことに対する偏見と、自伝の形式がもつ男性優位的な権威性をうかがわせる。ブリテンの作家としての成功は、男の歴史を書くことでなされた。ブリテンは看護師として、そして銃後の市民としてこの戦争を二つの視点で目撃したが、その観察対象が一貫して戦死した男たちだった点は、家父長制や男性権威主義的な思想から脱却できないブリテンの限界であると指摘できる。
しかし同時に、ブリテンは、彼女の世代全体を描くことで戦死した男たちという失われた声を再生し、公的なものにした。それによって公の歴史に抑圧された人々の証言を一つの「歴史」として確立しようとしたことは、この自伝の形式がもつ社会的な効用でもあった。
シンポジウム要旨
「曖昧さの魅力」――モダニズム期の女性作家たち
| 司会 | 神戸市外国語大学教授 | 御 輿 哲 也 |
| 講師 | ノートルダム清心女子大学講師 | 松 井 か や |
| 講師 | 神戸大学准教授 | 奥 村 沙 矢 香 |
| 講師 | 相愛大学准教授 | 石 川 玲 子 |
ウィリアム・エンプソンの画期的業績以来、「曖昧さ」(ambiguity)の存在が、すぐれた文学の本質と深くかかわることを疑う者はあるまい。だが、そもそも整然たる分類整理には馴染まぬはずの「曖昧さ」を、わざわざ七つの型にまで区分けして論じてみせたエンプソンの真意を推し量ることは、必ずしも容易なことではないはずだ。
元来奇をてらうところのあった詩人批評家のこと、ここでも手のこんだ悪戯にかまけているだけと見なせなくもないのだが、「曖昧の分類」という、ほとんど撞着語法を思わせる振る舞いの背後には、もう少し大きくて厄介な問題が隠れているように思える。数百にもおよぶ実例の細部にわたる徹底した分析を通して、恐らく何よりもエンプソンが示そうとしたのは、「曖昧さ」を安易に論じることの危険と周到に論じ尽くすことの困難、そしてそれにもかかわらず読者を分析や解釈の方へと駆り立てずにはおかない「曖昧さ」特有の蠱惑的で挑発的な魅力に他ならなかったのではないか。
三人の女性作家の「曖昧さ」について比較考察しようとしている私たちもまた、こうした「蠱惑」の罠にはまってしまったにすぎないのかもしれない。しかし出自も境遇も作風も異なる作家たちが、揃ってある種の曖昧な表現や不透明な描写に魅せられていたらしいという事実には、簡単には看過できない重みが感じられよう。「語られていることより語られていないこと」、「見えるものより見えないもの」、「意識されることよりされえないこと」の方に向けて絶えず心を傾けていた三人の作家の作品の具体的な分析を通して、その共通点と相違点がはらむ意味をさぐると同時に、彼女たちがそれぞれの「曖昧さ」によって描きとろうとしたものの実体を、たとえわずかであっても垣間見ることを私たちの課題としたい。(御輿哲也)
暴力の向こう側―エリザベス・ボウエンの短編に現れる曖昧な世界
松井かや
エリザベス・ボウエンと「曖昧さ」というテーマは非常に親和性が高いのだが、それは彼女の出自がアングロ・アイリッシュであることと無関係ではなかろう。アイルランドのかつての支配階級プロテスタント・アセンダンシーの一員であり、ビッグ・ハウス「ボウエンズ・コート」の最後の継承者としてアイルランドとイギリスを可能な限り行き来する人生を送った彼女は、自身が最も安心できるのは「アイリッシュ海の真ん中にいる」ときだと述べた。アイルランドにも、またイギリスにも完全に属しきれない彼女の存在そのものに付き纏うこの曖昧さは、作家としての彼女に独自の視点をもたらしたはずである。
本発表では、殺人事件というセンセーショナルな出来事を(おそらくは)核とする二つの短編 “Recent Photograph” (1926) と “Look at All Those Roses” (1941) を取り上げ、そこに立ち上がる何とも不可解かつ曖昧な世界の分析を試みたい。ボウエンの多くの短編がそうであるように、この二つもミステリーの要素を色濃く持ち、読者は謎解きへと誘われるが、その謎は解き明かされることはなく、語られるほどに事実はその輪郭を失っていく。殺人という大きな暴力を扱いながら/仄めかしながら、ボウエンはその向こうにどのような世界を呈示しようとするのか。彼女がいわゆる「国際的な」モダニズムに触れながら、同時に「アイリッシュ・モダニズム」の流れの中に身を置くことを踏まえて、その「曖昧な」世界を考えてみたい。
ウルフと/のうたた寝――『歳月』と『幕間』を中心に
奥村沙矢香
ウルフの作中人物は、とにかくよく眠る。このことは、モダニズム文学が不眠(症)のモチーフ――例えばT. S. エリオットの詩における夜歩きのような――に彩られているという事実に照らしてみれば、いささか奇妙なように思える。加えて、ウルフの描く眠りの多くが軽い眠り(うたた寝)であるということに注目するならば、興味深いことが見えてくる。『自分自身の部屋』の一節、「無為に過ごしている時、夢見ている時にこそ、隠れていた真実が時として表面化するものだ」に端的に示されるように、ウルフの作品世界は眠りと覚醒のあわいに位置している。うたた寝は、いわばその世界が眠りの領域に軽く一歩、踏み込む瞬間であろう。その瞬間が作中人物の行為として繰り返し可視化されるとき、その描出は「あわい」の発する美学的主張とはまた別の、確かなメッセージ性を帯びるようである。本発表では、眠りがとりわけ意義が捉えがたく曖昧な振る舞いとして描かれる『歳月』と『幕間』に焦点を当て、その描写が当該作品の重要なテーマへと、ひいては同時代に対するウルフの社会的・文化的スタンスの表明へと接続する可能性があることを示したい。
キャサリン・マンスフィールドの「結婚」と「家庭」に見る曖昧さ
石川玲子
キャサリン・マンスフィールドの作品の中には、夫婦、あるいは結婚に至る手前の男女を扱ったものが多くある。その種の物語に現れる曖昧さは、それらの男女の関係や心の動きが複雑な捉えがたさを呈していることに起因しているように思われる。そして、そうした彼らの意識あるいは無意識に大きく影響を及ぼしているのは、「結婚」という制度、あるいはそれによって作り上げられる「家庭」という概念なのではないか。
このことは、マンスフィールドが生涯を通して幸せな結婚と家庭に恵まれることがなかったことと無関係ではないだろう。ニュージーランドの中産階級の家庭における父と母の関係や、両親と彼女自身の心理的な葛藤は、恐らく彼女の中に「結婚」と「家庭」に対する複雑な思いを植え付けたに違いない。また、ロンドンで単身作家の道を志した彼女は、同郷のチェリスト、ガーネット・トラウェルとの子供を宿すが、彼との結婚は実現しなかった。ほどなく音楽教師ジョージ・ボウデンの求婚を受け入れるが、彼女は「結婚」という制度をシェルターとして利用したに過ぎず、その形だけの結婚が後に、心から望んだJ.M.マリとの結婚の障壁となったことは皮肉である。漸く離婚が成立してマリとの結婚を果たすが、病が主な原因となって、その結婚も心安らぐ「家庭」を彼女にもたらしてくれることはなかった。本発表では、 “Bliss” (1918)や “Revelations”(1920)など夫婦や結婚前の男女を扱った短編が孕む曖昧さの奥にあるものを、マンスフィールド自身の経験に照らしながら考えたい。
特別講演要旨
『幕間』における田園主義的イングリッシュネス――ナショナリズムと戦争
法政大学教授 丹治愛
かつて修論の一章として神話批評的な論文を書いた『幕間』を、ほぼ40年をへた今、もう一度とりあげたいと思ったのは、第二次世界大戦がはじまる直前の、「イングランドの中心」の田園のなかで、イングランドの歴史が「パジェント(野外歴史劇)」として再現される一日を描いたこの小説を、田園主義的イングリッシュネス概念の歴史のなかに置き直すことによって、この小説(のとくに結末)を神話批評とは異なるかたちで解釈できるのではないかと考えたからである。『三ギニー』でナショナリズムと戦争のあいだの関係を論じたウルフは、ナショナリズムとともに強化された田園主義的イングリッシュネス概念を、『幕間』のなかでいったいどのような目で見ているのだろうか。