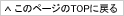2015年度
第35回全国大会 プログラム
| 日時 | 2015年10月17日(土)10:00~18:20 |
|---|---|
| 場所 | 青山学院大学 青山キャンパス 総研ビル11階 第19会議室 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25 |
| 交通 | ■ JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線 他 「渋谷駅」より徒歩10分 ■ 東京メトロ(銀座線・千代田線・半蔵門線)「表参道駅」北口より徒歩5分 |
| 受 付 (9:30~10:00) | ||
| 開会の辞 (10:00) | ||
| 成蹊大学教授 | 遠 藤 不 比 人 | |
| Ⅰ 研究発表(10:00~12:10) | ||
司会 |
京都女子大学教授 | 廣 田 園 子 |
| 「他者」との遭遇――Katherine Mansfieldのマオリ表象 | ||
| 長崎大学戦略職員(コーチングフェロー) | 大 谷 英 理 果 | |
| 「バラを愛することはアルメニア人を救うことにはならないか」 ――『ダロウェイ夫人』における芸術によって表現される体制批判 |
||
| 奈良女子大学大学院生 | 豊 田 麻 美 | |
司会 |
津田塾大学准教授 | 秦 邦 生 |
| 使用人の肖像――Virginia Woolfと「使用人問題」 | ||
| 京都女子大学非常勤講師 | 大 西 祥 惠 | |
| ドリス・レッシングの『暮れなずむ女』に現れる母娘関係 | ||
| 一橋大学大学院生 | 関 野 佳 苗 | |
| Ⅱ 総 会(13:40~14:00) | ||
司会 |
成蹊大学教授 | 遠 藤 不 比 人 |
| 会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他 | ||
| 大手前大学教授 | 太 田 素 子 | |
| Ⅲ 開催校挨拶(14:00) | ||
| 青山学院大学文学部長 | 折 島 正 司 | |
| Ⅳ シンポジウム(14:10~17:20) | ||
| 「ブルームズベリー・グループと音楽文化――ウルフ、オペラ、スペクトラル音楽」 | ||
司会・講師 |
都留文科大学准教授 | 加 藤 め ぐ み |
講師 |
同志社大学教授 | 山 本 妙 |
講師 |
共立女子大学専任講師 | 浦 野 郁 |
講師 |
上智大学非常勤講師 | 小 室 龍 之 介 |
| 閉会の辞(17:20) | ||
会長 |
大手前大学教授 | 太 田 素 子 |
| Ⅴ ミニ・コンサート(18:00~18:20 於:懇親会場) | ||
| Dominick Argento From the Diary of Virginia Woolf(1975)より 1.The Diary 2.Anxiety 8.Last Entry |
||
出演 |
武蔵野音楽大学准教授(Sop.) | 佐 橋 美 起 |
| ピアノ | 原 島 滋 子 | |
| 懇 親 会(18:20~20:20) | ||
会場Trattoria La Fenice Wai Wai(ラ・フェニーチェ ワイワイ) |
||
| 会費6000円(学生3500円) | ||
研究発表要旨
「他者」との遭遇-Katherine Mansfieldのマオリ表象
九州大学大学院博士後期課程(長崎大学コーチングフェロー) 大谷英理果
“How Pearl Button was Kidnapped”は、1912年9月に『リズム』誌に掲載されたKatherine Mansfieldの作品である。この作品は、「箱の家」(“the House of Boxes”)に象徴される閉鎖的で抑圧的な白人(パケハ)の社会から太った2人の女性によりPearl Buttonが連れ出され、開放的で原始的な新たな世界を経験する通過儀礼的な語りであると言える。Pearlは、他者と出会い、未知なる海にも触れ、これまで感じたこともない幸せを感じるものの青い服を着た小さな男たちによって、「箱の家」が象徴する白人社会へ連れ戻されることが暗示され物語は終わる。
作品内に登場する原色の服を着た太った女性は、“dark women”と描写されることはあるが、その人種・民族性は作者によって明言されてはいない。しかし、その女性たちの身なりや所持品からニュージーランドの先住民であるマオリの人々をMansfieldが描写しているということは先行研究によりすでに明らかである。Mansfieldのマオリ観を知る上で避けて通ることのできない重要な課題は、彼女が1907年に行ったニュージーランド北島のUrewera地域などへのキャンプ旅行(1ヶ月間)において、自身の旅を記録したノートの分析である。この旅を通し、彼女はマオリの人々と遭遇し、熱心にマオリの人々やその生活様式をノート内に記録している。Ian A. Gordonは、Mansfieldがこの旅行体験を記録していたノートを書き起こし、The Urewera Notebook (1978)としてまとめている。The Urewera Notebook (以下、Notebook)に見られるMansfieldのマオリ観はAnne Maxwellによって示唆に富む分析がなされているが、Mansfieldのマオリ観が彼女の短編小説においてどのように反映されているのかということまでは分析がなされていない。そこで本発表では、Notebookに記録されているMansfieldのマオリの人々との出会いとPearl Buttonの成長過程を比較しながら論じることで、“How Pearl Button was Kidnapped”に描写されるマオリ像について再考したい。その際に、旅行中に垣間見たマオリの人々が抱える問題などMansfieldが、Notebookには記録しているにも拘わらず作品内においては隠蔽したと言えるマオリ像についてまず分析を行いたい。そのことにより、Mansfieldの肯定的なマオリ観のみに焦点が当てられることが多かった本作品の従来の研究において見落とされてきたMansfieldのアンビバレントなマオリ表象を明らかにしたい。
MaxwellがNotebookの分析において指摘するように、Mansfieldは、「雑種性」(ハイブリディティ)を嫌う傾向があり、白人入植者が先住民に及ぼす影響力の強さをこの旅行を通してネガティブに捉えている。そのことは、“How Pearl Button was Kidnapped”におけるプリミティブなマオリ像に如実に反映されている。しかし、Notebookにおいて、Mansfieldは、マオリの人々が直面している課題も記録していると言える。例えば、西洋化される彼らの生活様式である。また、マオリの人々の身体的な美しさを記録する時もあるが、同時にマオリの人々の体の弱体化も記録している。19世紀末にはマオリの人口が激減したことによりマオリ絶滅説がささやかれていた時代背景も踏まえると、Mansfieldが記録しているマオリの人々の身体的な衰退は当時のマオリを取り巻く社会問題であったと言える。しかし、“How Pearl Button was Kidnapped”にはこれらのマオリの人々の問題は一切描写されていない。これらの問題の隠蔽は、本作品内で、Mansfieldが、Pearlが住む閉塞的なパケハ社会(パケハ中心主義)を批判するために、明らかにパケハとは大きく異なるオーセンティックなアイデンティティを持つ「他者」として理想的でピュアなマオリ像を創出するために行われたものであると考えられる。しかしそのことは同時にマンスフィールドのマオリ描写は、抽象的で、文明に汚されていない無垢な先住民というステレオタイプ化された西洋の表象(ある種の「プリミティビズム」)を強固なものにしているだけであるという問題を孕むことになる。本発表では以上に挙げた内容を中心に考察した上で、Mansfieldのアンビバレントなマオリ観が白人優位主義の再構築とも解釈できる“How Pearl Button was Kidnapped”の結末と深く結びついている点を示したい。
「バラを愛することはアルメニア人を救うことにはならないか」
―『ダロウェイ夫人』における芸術によって表現される体制批判
奈良女子大学大学院生 豊田麻美
ヴァージニア・ウルフ(Virginia Woolf, 1882-1941)は『ダロウェイ夫人』(Mrs Dalloway, 1925)執筆時に “I want to criticize social system”と日記に記しており、この記述は彼女が当時のイギリスに対する批判を『ダロウェイ夫人』に込めていたことを明らかにしている。本発表ではこのウルフの社会批評の試みに注目し、特に多大な犠牲を英国国民に強いた第一次世界大戦を導いた、当時のイギリスの支配階級への批判が作品内でどのように表現されているのかを考察する。
『ダロウェイ夫人』の背景となっている20世紀初頭のイギリスは、不況や大戦のために危機に陥っていた。Michael H. Whitworthによると、そのような状況下では大英帝国の威信を保つために「全体の利益を守るためなら、個人の自由を多少制限してもかまわない」という概念が生まれ、やがて社会に浸透していった。リベラルな思想の持ち主であったウルフはこの風潮に我慢できず、作品内に抑圧者としての支配者層と、個人の自由を求めてそれに抵抗もしくは拒否する人々という対立を作品中に描くことで社会を動かす権力者を間接的に批判している。このことは、支配階級に属しているはずの主人公を被抑圧のグループに含めることで、さらに強調されている。
これまでもLee. R. EdwardsやSusan M. Squierなどが、冷酷な権力者層と抑圧に抵抗する芸術を愛し感受性豊かなクラリッサの対立に注目してきたが、EdwardsとSquierはこの対立項に「政治を行う権力者層=男性の世界」と「家庭にこもりパーティーを開くクラリッサ=女性の世界」という二項対立をあてはめ、ジェンダーの観点から分析を行っている。
本発表では、同じようにヒロインと権力者の対立に焦点をあてるが、ジェンダーの観点からというよりも、ウルフが社会批判の方法として、バラや文学等、作品に現れる芸術に関するモチーフを使ったことに注目して分析を行いたい。なぜなら、ウルフは人々を抑圧する権力者層に「無感覚さ」を、権力者層に反抗的な思想を持つ人々に「鋭い感受性」という属性を与えおり、作品全体を通して芸術や文学などに感動できる心を持っているかどうかは非常に大きな問題として扱われているからである。
ウルフの芸術に関するものを使用した批判の例として、当時世論を騒がしたトルコ人によるアルメニア人の虐殺問題に対するクラリッサの反応を記した一文があげられる。夫がくれたバラの花束を抱えながら彼女はアルメニア人の虐殺に対してはなんの興味も持てないけれどもバラなら大好きだ、と思う。そして “didn't that help the Armenians?”と呟くのである。この発言は一見、政治の知識がない有閑夫人の軽率な発言に聞こえるが、実は体制側への痛烈な批判ともとれる。なぜならバラや芸術などに感動できない「無感覚さ」は彼らの想像力の欠如を暗示し、その想像力の欠如ゆえに他人のことを思いやることが出来ずアルメニア人虐殺のような恐ろしい事態が起きたともとれるからである。そしてこのアルメニア人虐殺への批判は当時のイギリス社会にもあてはめて考えることも可能である。芸術に関心のないイギリスの支配者層も他人を思いやる想像力がないばかりに、大戦中、国民に無理な自制を強要し個人を抑圧するイギリス社会を作る事になったともいえるからである。本発表ではこの例のように、クラリッサの感受性をかきたてるモチーフに注目しながら、支配者層を批判するときに芸術にかかわるものが作品内でどう働いていたかを示したい。
使用人の肖像―Virginia Woolfと「使用人問題」
京都女子大学非常勤講師 大西祥惠
Virginia Woolf(1882-1941)は、“Character in Fiction”(1924)の中で「1910年の12月かその頃に、人間の性質は変わった」と述べているが、その「人間の性質」の変化の例としてヴィクトリア朝とジョージ朝の料理人の違いを挙げている。この使用人たちの変化がもたらしたものの一つが、当時、深刻化していた「使用人問題」である。ヴィクトリア朝に絶頂にあった使用人文化は、第一次世界大戦を境に大きな転換期を迎える。戦争中、それまで男性たちがしていた多くの仕事が女性たちに解放され、低賃金で過酷な家事使用人の仕事は、他の仕事より劣ったものだと考えられるようになり、家事使用人の多くが他の仕事に就くようになる。そして要求が多く、雇い主に従順でなくなった使用人たちは、多くの家庭の悩みの種となっていた。
ウルフもまたこの「使用人問題」に苦しんでいた。この問題は、ウルフ家では「ネリ―問題(the question of Nelly)」と呼ばれ、ウルフと料理人のNellieの間では絶えず戦いが繰り広げられていた。ウルフはネリ―のような「教養のない」人間が「生活の中に入ってくる」と嫌悪感を日記の中につづり、使用人制度に疑問を投げかけている。このようにウルフが使用人に嫌悪感を抱き、使用人からの解放を願っていた一方で、彼女は使用人に依存し、使用人たちは、ウルフの欲望の対象でさえあった。ウルフは「ネリ―の肖像」を描き出すことで「物語を作りたい」という「欲望」を日記の中で露わにしている。ウルフが使用人に抱いていた「欲望」と「嫌悪」というアンビバレントな感情は、アンビバレントな使用人の肖像となってテクストの中に表れているように思われる。
それが極めて顕著なのが、Mrs Dalloway(1925)の使用人の描写である。「緑色の目をした」「残忍な怪物」と呼ばれ、Clarissa Dallowayの心の平安を乱す存在として登場するクラリッサの娘の家庭教師のDoris Kilmanが描かれる一方で、ダロウェイ家の多くの使用人は、彼女に従順であり、彼女と信頼の絆で結ばれている。『ダロウェイ夫人』やTo the Lighthouse(1927)に見られるこうした使用人たちに慕われる女主人たちとは異なり、実生活の中で、ウルフは使用人たちの望むような女主人であったとはいえなかったようである。女主人と使用人の関係のこうした理想と現実のゆがみは、ウルフのテクストの中に投影されているように思われる。
これまでウルフと使用人との関係を分析したものは、ウルフの私生活での使用人との関係を論じたAlison LightのMrs Woolf & the Servants(2007)やStephen家の料理人であったSophieをモデルにしたウルフの未刊の短編“The Cook”に焦点を当てたSusan Dickの“Virginia Woolf's ‘The Cook’”(1997) とClara Jonesの“Virginia Woolf's 1931 “Cook Sketch””(2014)、ウルフの様々な短編での使用人の表象を研究したHeather LevyのThe Servants of Desire in Virginia Woolf's Shorter Fiction(2010)などがあるが、ウルフの主要な小説における使用人の表象については十分に議論されていない。したがって本発表では、ウルフの小説の中でも使用人が多く登場する『ダロウェイ夫人』、『灯台へ』、Flush(1933)を主に扱い、ウルフの描く使用人の肖像について考えていきたい。
ドリス・レッシングの『暮れなずむ女』に現れる母娘関係
一橋大学大学院生 関野佳苗
ドリス・レッシング(Doris Lessing, 1919-2013)はその長い執筆活動の中で、小説だけでなく、ノンフィクション、劇作と多岐にわたって活動を行った女性作家である。本発表では、彼女が1973年に出版した『暮れなずむ女』(The Summer Before the Dark, 1973)を取り上げ、この作品で描かれる母娘関係について考察を行う。この作品以降、レッシングはロンドンを思わせる荒廃した都市を描いた『生存者の回想』(The Memoirs of Survivor, 1974)やスペース・フィクションと呼ばれている『アルゴ座のカノープスシリーズ』(Canopus in Argos: Archives, 1979-1983)を執筆し、リアリズム小説から一度距離をとっている。しかし、レッシングが再び『夕映えの道―よき隣人の日記』(The Diary of a Good Neighbour,1983)でリアリズムの手法に立ち返り、世代の異なる女性同士の連帯を描いていることを考えれば、『暮れなずむ女』は女性の連帯へのレッシングの姿勢を考えるうえで重要だといえるだろう。
『暮れなずむ女』では、40代の主人公ケイトが家庭から離れて過ごしたひと夏が描かれる。夫や3人の子供たちが夏の間にロンドン郊外の家を離れるのに合わせ、ケイトはひとり通訳者として国際会議で働き始める。妻として、母として家族のために働いてきた彼女は働く女性へと姿を変え、その後、イスタンブールやスペインをめぐり、イギリスへ帰国後、再び自宅に戻るまでの残りの時間を自分の娘と同年代の女性モーリーンと過ごす。家族から離れて経験したこのような出来事を通して、この作品は、ケイトが自己の在り様、つまりはアイデンティティを見出す物語であると考えることができる。この文脈からいえば、女性が家族から離れ、自らのアイデンティティを発見するという形をもって、この作品は女性の解放を描いているといえるだろう。しかし、ケイトが小説の最後に、同居していたモーリーンにさえも気づかれず、ひっそりと家族のもとへと帰っていくことに注目すれば、このような肯定的な読みには疑問を持たざるをえない。
したがって、本発表ではこの作品を主人公ケイトが解放された物語であると捉える肯定的な批評とはある程度距離を置き、彼女がひと夏をかけた旅の最後の場所としてたどり着いたモーリーンのフラットの表象にまず注目する。医者の妻であるケイトが買うことを戸惑う二流品がスーパーに並ぶような地区の地下に存在するモーリーンのフラットは、階級的、位置的にも外界から切り離された場所である。そこでケイトはどこか不信感を取り除けないでいる夫や、すでに親の世話を必要としない子供たちがいる家族のもとへと帰る意味に初めて向き合うこととなる。そのような場所でモーリーンはケイトを年取った女性として特別視せず、二人は世代を超えた友情を築いている。
しかし、小説の終盤で二人の友情は、血がつながっていないにもかかわらず、母と娘の対立へと変化していってしまう。つまり、モーリーンのフラットという階級的、社会的なしがらみから切り離された場においても、母娘関係が世代の異なる女性の間に現れてくるのである。以上のように、本発表ではモーリーンの部屋の表象から、その場で起こるケイトとモーリーンの関係性の変化を考察し、彼女たちの連帯が母娘の対立関係へと変化し、失敗に終わる過程を再考していきたい。
第35回 日本ヴァージニア・ウルフ協会大会シンポジウム要旨
「ブルームズベリー・グループと音楽文化――ウルフ、オペラ、スペクトラル音楽」
| 司会・講師 | 都留文科大学准教授 | 加藤めぐみ |
| 講師 | 同志社大学教授 | 山本妙 |
| 講師 | 共立女子大学専任講師 | 浦野郁 |
| 講師 | 上智大学非常勤講師 | 小室龍之介 |
“I always think of my book as music before I write them.”(L6: 425)――1940年、ウルフが『ロジャー・フライ伝』執筆中に友人のヴァイオリニストに宛てた手紙に綴ったこの一節は「ウルフと音楽」について語る際にしばしば引用される。ウルフはどんな音楽をイメージしながら執筆活動をしたのか、あるいは音楽を奏でるように言葉を紡いだのか。ブルームズベリー・グループのメンバーたちは、いかに音楽と関わり、それが彼らの執筆、芸術活動にどんな影響を及ぼしたのか。これまで文学、視覚芸術との関連で論じられることの多かったウルフ、そしてブルームズベリー・グループだが、近年「音楽文化」との関係に注目が集まっている。この傾向は、過去数年の間にEmma Sutton, Virginia Woolf and Classical Music (Edinburgh UP, 2013)、Sam Halliday, Sonic Modernity: Representing Sound in Literature, Culture and the Arts (Edinburgh UP, 2014)、Adriana Varga, Virginia Woolf and Music(Indiana UP, 2014)などの研究書が相次いで出版されていることからも明らかである。こういったブルームズベリー・グループと音楽文化への関心の高まりの背景に、20世紀初頭の英国におけるヨーロッパの前衛的な現代音楽(ストラヴィンスキーやシェーンベルクなど)の受容の再検証、Retrospect Opera(retrospectopera.org.uk)の活動に見られるような歴史に埋もれつつある英国音楽、オペラを再評価、再上演しよう、といった動きがあることも看過できないだろう。
いま、なぜ「ブルームズベリー・グループと音楽文化」なのか――本シンポジウムでは、まず司会兼講師の私が、近年の研究動向を整理した<マッピング>を示し、そのうえで、さらに先を行く研究を「ブリテン、スマイズのオペラ、フォースター、ウルフ、スペクトラル音楽」をキーワードに、各講師から映像を交えてご提示いただく。単に文学テクストと楽曲とを併置するにとどまらない「文学と音楽の新しい読み」がそこで展開されるはずである。そしてシンポジウム終了後、学会会場から懇親会場へと場所を移し、本シンポジウムの特別企画として「ミニ・コンサート」を行う。ミニ・コンサートではアメリカの作曲家ドミニク・アルジェント(Dominick Argento, 1927-)によるFrom the Diary of Virginia Woolf(1975)全8曲のうち3曲(1.The Diary 2.Anxiety 8. Last Entry)を、国内外でご活躍のオペラ歌手、佐橋美起先生の生演奏でお届けする。ピューリッツァー賞の受賞作であるFrom the Diary of Virginia Woolf については、A Writer’s Diary (1953)との比較、上演史、先行研究の概要などを、シンポジウム最後に私から紹介したうえでご鑑賞いただく予定である。(文責:加藤めぐみ)
20世紀のイギリス・オペラの興隆――ブリテンから振り返るスマイズ
山本 妙
エセル・スマイズ(Ethel Smyth, 1858-1944)の音楽作品をウルフはあまり高く評価しなかったようである。しかし、ウルフがブリテンのオペラ Peter Grimes(1945)を聴くことができたなら、共感を覚えたのではなかろうか。ブリテンは、言葉と音楽を密接に結びつけ、共同体が個人に振るい得る暴力やセクシュアリティの問題などを作品化し、イギリス・オペラを復興(創生)する役割を果たした。その前哨戦ともいえる位置にあるのが、1900年代に完成されながら、演奏される機会の少なかったスマイズのThe Wreckersであると考える。音楽的な新しさを本格的に論じることは発表者には難しいが、両作品は似通った要素をもっている。一方、音楽家として英国での処遇と言う点では、両者は対照的でもある。ブリテンから振り返って、スマイズの音楽を紹介し、イギリスのオペラ興隆について考えたい。
老船長は回想し、歌う――オペラBilly Buddにおける欲望の行方
浦野郁
ベンジャミン・ブリテン(Benjamin Britten, 1913-1976)のオペラBilly Budd(1951年初演)の台本を、Eric Crozierと共にE. M. Forsterが担当したことはそれほど知られていない。このオペラ化に当たり三者が最も気を配ったのが、船長Vereを原作者Herman Melvilleから「救い出し」、より人間的な葛藤を抱く人物として描くことだった。そのためオペラ版は全編がVereの回想という形を取っている。本発表では、いくつかの場面を実際に鑑賞し、この変更により作品が語り手Vereの自己欺瞞の物語とも捉えられるようになったことを指摘する。その上で、同時期に書かれ海を舞台とするForsterの短編“The Other Boat”や、W.H. Audenらアメリカに渡った友人達との交流にも目を向け、戦後イギリスで同性間の欲望を描くことがどの程度まで困難であったかを考えてみたい。
オカルト、音楽、ウルフ
――19世紀の心霊主義からイタリア未来派、そしてスペクトラル音楽まで
小室龍之介
不可視で触れることもできないゆえ、物理的には空気の振動に過ぎない音はオカルトの道具であった。このことは19世紀に英国で流行した心霊主義、また、1914年にロンドンでコンサートを開催した伊・未来派の一人で『騒音の芸術』で知られるルイジ・ルッソロ(Luigi Russolo, 1885-1947)について当てはまる。さらに、その残党で作曲家のジャチント・シェルシ(Giacinto Scelsi, 1905-1988)にこの傾向は引き継がれたようだ。彼は、ヴァージニア・ウルフを含むサークルに足を運んだと言われ、東洋の心霊主義に傾倒した。倍音や微分音を駆使し、通常では存在しえない音を探求したスペクトラル音楽の先駆者である。
本発表では、19世紀の心霊主義や未来派、そしてその残党が不可視な音をどのように利用し制作したかを紹介し、ウルフ作品に立ち現れるオカルトの音について触れ、モダニズム期の文学や音楽における不可視の音について論じてみたい。