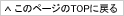2014年度
第34回全国大会 プログラム
| 日時 | 2014年11月16日(日)10:30~17:00 |
|---|---|
| 場所 | 相愛大学 学生厚生館 S-307 〒559-0033 大阪市住之江区南港中4丁目4-1 |
| 交通 | ■大阪駅 →(JR環状線8分)弁天町 →(地下鉄中央線9分)コスモスクエア →(ニュートラム7分)ポートタウン東 ■西梅田 →(地下鉄四つ橋線21分)住之江公園 →(ニュートラム11分)ポートタウン東 ■新大阪 →(梅田経由、地下鉄御堂筋線17分)大国町 →(同じホーム向かい 四つ橋線12分)住之江公園 →(ニュートラム11分)ポートタウン東 ■関西国際空港 →(リムジンバスで40分)ポートタウン東 ■ポートタウン東駅より徒歩3分 |
| 受 付 (10:00~10:30) | ||
| 開会の辞 (10:30) | ||
| 相愛大学准教授 | 石 川 玲 子 | |
| Ⅰ 研究発表(10:30~12:30) | ||
司会 |
大手前大学教授 | 太 田 素 子 |
| ヴェールを破るパーシヴァル――The Wavesにおける内的ヴィジョンの顕現 | ||
| 九州大学大学院生 | 原 田 洋 海 | |
| “I'd Forgotten the Raid!”——―ウルフ『歳月』と忘れられた大戦 | ||
| 東北学院大学大学院生 | 畠 山 研 | |
司会 |
成蹊大学教授 | 遠 藤 不 比 人 |
| 21世紀に読み直される『ダロウェイ夫人』 | ||
| 近畿大学特任講師 | 高 橋 路 子 | |
| ウルフとリチャードソン――二人の前衛作家の映画への視線 | ||
| 青山学院大学准教授 | 大 道 千 穂 | |
| Ⅱ 総 会(14:00~14:15) | ||
司会 |
九州大学教授 | 鵜 飼 信 光 |
| 会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他 | ||
| 東京家政大学教授 | 伊 藤 節 | |
| Ⅲ シンポジウム(14:15~17:00) | ||
| 「メタモダニズム」とは何か ――現代文学とウルフそして/あるいはモダニズムの「継承」という問題 |
||
司会・講師 |
津田塾大学准教授 | 秦 邦 生 |
講師 |
京都女子大学准教授 | 廣 田 園 子 |
講師 |
慶應義塾大学専任講師 | 近 藤 康 裕 |
講師 |
大阪大学准教授 | 山 田 雄 三 |
| 閉会の辞 (17:00) | ||
会長 |
東京家政大学教授 | 伊 藤 節 |
| 懇 親 会 (17:45~19:45) | ||
会場コスモスクエア国際交流センター |
||
| 会費6000円(学生3500円) | ||
研究発表要旨
ヴェールを破るパーシヴァル ―The Wavesにおける内的ヴィジョンの顕現
九州大学大学院生 原田 洋海
主人公6人によるDramatic Soliloquyによって成り立つ『波』(The Waves 1931)の特殊な小説形態をウルフが確立するまでの過程については那須雅子氏が詳しく論じており、またこのDramatic Soliloquyという形式において、ウルフが「自分の言いたいこと」すなわち内的ヴィジョンを作中に表現できたことについても指摘している。この作品は内面描写を追求してきたウルフ作品の集大成ともいえるが、本発表では、内面描写を追求して書かれた本作中において、内面がいかにして外部に伝達されうるかを考察したい。
まず、6人の内的ヴィジョンの顕示を妨げているものについて考察する。『波』について論じる前に、ウルフが『灯台へ』(To the Lighthouse 1927)において、感情を正確に言葉で伝えることの不可能性について、ラムジー夫人とリリー・ブリスコーを通じて何度も訴えていることを確認しておく。特に、ラムジー夫人は「洗練された気遣いの薄いヴェール」で言葉を覆わなければならないと考えており、ゆえに発せられた言葉は必ずしも真実を伝えないと思っている。このようなヴェールは、意識的にせよ無意識的にせよ、真実を覆い隠してしまうのである。『波』においても“veil”という言葉の多用がマリア・ディバティスタ(Maria DiBattista)によって指摘されているが、『波』の登場人物たちはヴェールに限らず、何らかの方法によって自らの感情や内的ヴィジョンを覆い隠している。例えば、バーナードは句を作り上げることによって、ジニーはドレスや化粧で身体を包むことによって、スーザンは感情をハンカチにくるむことによって、ネヴィルは世界に秩序や区別を見出すことによって、ローダとルイスは他者を真似ることによって自らを隠してしまっている。他のウルフ作品にも共通しているように、彼らもまた社会的役割、特にジェンダー的役割に応じて自己を偽装しているのである。
このように自己を覆い隠す6人と対照的であるのがパーシヴァルである。父権社会や帝国主義の表象として見られることも多いパーシヴァルであるが、一方で、そのようなイデオロギーに強制される自己偽装のヴェールを破る存在でもある。ディバティスタやマキコ・ミノー=ピンクニー(Makiko Minow-Pinkney)が指摘しているように、その名前は‘pierce the veil’すなわち彼が6人のヴェールに穴を穿つ存在であることを意味している。パーシヴァルの存在が詩的霊感を与え、6人に自らの感情や内的ヴィジョンを言い表す機会を与え、特にインドに赴くパーシヴァルの送別会の場面でそれが顕著である。また、パーシヴァルは他者の真似をせず、晩餐会でも正装をせず、いわば他の6人と違って外的世界に合わせて自己を偽ることがない。彼は他者のヴェールだけでなく、彼自身のヴェールをもすでに打ち破っているのである。全く内面描写のない、彼らにとって外的な存在であるパーシヴァルよって彼らの内面は顕示されうる。パーシヴァルの存在と彼の死について再考することは、内面しか描かれない彼ら6人の外的世界との関係性をより明らかにすることになるのである。
本発表では、主要登場人物6人を覆うヴェールと、それを突き破るパーシヴァルという構図に焦点を当て、外からの刺激によって内的ヴィジョンが言葉として表現されうることを示したい。
“I'd Forgotten the Raid!” ——ウルフ『歳月』と忘れられた大戦
東北学院大学大学院生 畠山 研
ヴァージニア・ウルフ(Virginia Woolf, 1882-1941)の『歳月』(The Years, 1937)は、19世紀末から20世紀前半にかけて、英国に暮らすある中産階級パージター家の歴史を描く物語である。物語は「1880年」と題のつくセクションから始まり、およそ1930年代と推測される「現在」まで続く。そのあいだ、新世紀初頭のヨーロッパでは空前の犠牲を払った第一次大戦が起きたが、それは物語内でも「1917年」と「1918年」のセクションで描かれており、特に前者では一家の長女エリナの従姉妹夫婦の家でドイツの空襲を警戒しながら晩餐をする場面がある。
注目すべきは、晩餐後、一同が解散するとき、エリナが“I'd forgotten the raid!”と言って、空襲を忘れてしまうことである。一見すると、彼女にとって戦争の脅威はそこまで深刻ではなく、銃後の人々の戦争意識の低さを露呈するかもしれない。しかし、エリナは従姉妹の家へ着く前に戦争に思いをめぐらせており(“I was thinking [about this war] as I came along in the bus”)、晩餐中も、甥ノースの出征の知らせや鳴り響く砲声によって絶えず戦争を意識せざるをえない状況下に置かれていて、実際、従姉妹マギーの夫ルニーに向けて戦争に言及していたことからもわかるように(“Could you allow the Germans to invade England and do nothing?”)、大戦について確かな意識や関心が示されていた。そのようななかで、一同が「新しい世界」を求めて乾杯したあと(“To the New World!”)、彼女は未来への自由を望むが(“We shall be free, we shall be free, Eleanor thought”)、この自由は、漠然とした新たな未来への期待という意味だけでなく、空襲のせいで避難先の地下室という閉塞的な空間で晩餐を強いられているものにとって、戦争からの解放も内包していると言える。このように考えると、エリナが空襲を忘れることは、ある意味では、彼女が望んだ戦争からの自由と解放になっていることがわかる。
本発表では、この忘却という第一次大戦からの自由あるいは解放という観点から『歳月』を考察してみたい。エリナが空襲を忘れたのは、マギーとルニーを見て、“A happy marriage. She [Eleanor] thought, that’s what I was feeling all the time”とあるように、理想的な夫婦像を見出したときであった。果たして、空襲下、この結婚のイメージに戦争の不安を打ち消す可能性はあるのか。理想的な結婚は、同性愛者ニコラスや結婚適齢期をとうに過ぎたエリナの立場とどのように関わるのか。戦争を忘れることは、今そこにある危機を意識しない現実逃避や思考停止なのか。兵士たちが戦う前線と非戦闘員が暮らす銃後の境界を不問にする空襲の爆撃は、第一次大戦後、現在も世界中で圧倒的な破壊力を保持しながら人々に不安をもたらすものだが、20世紀、21世紀の戦争からの自由と解放、真の平和は、エリナの忘却と同様、もはや人々の脳内でしか存在しえない実現不可能なものなのだろうか。エリナの記憶と忘却の問題は、Mark Hussey編Virginia Woolf and WarやKaren L. LevenbackのVirginia Woolf and the Great Warのような代表的な先攻研究では、後者でわずかながら言及があるものの、まだ十分議論されていない。本発表では、以上に挙げた内容を中心に、『歳月』と戦争の問題を再考する。
21世紀に読み直される『ダロウェイ夫人』
近畿大学特任講師 高橋 路子
Michael CunninghamのThe Hours (1998)、Robin LippincottのMr. Dalloway (1999)、John LancasterのMr. Phillips (2000)とIan McEwanのSaturday (2005)は、いずれもVirginia WoolfのMrs. Dallowayを下敷きにして書かれた作品である。先行テクストとの距離はさまざまだが、共通しているのは、ある一日の物語である点、登場人物の心の中で過去と現在が交錯する点、死、狂気、セクシュアリティなどがテーマとして扱われている点などである。たしかに、過去の文学作品を読み直すという作業は決して珍しくない。とりわけポストモダンの作品においては顕著な傾向である。しかし、21世紀に「なぜウルフなのか」「なぜ『ダロウェイ夫人』なのか」という疑問は残る。さらに、すべて男性作家によること、うち二人はゲイ作家でアメリカ人作家であること、四作品中三作品の主人公が男性であることにも何らかの意味があるように思われる。
『ダロウェイ夫人』が現代の作家たちによって再び取り上げられたことについては、ナラトロジーの観点から分析する研究もあるし、テーマごとに現代社会との関係性を分析する研究もある。また、先行テクストとの関係については、ブルームの「影響の不安」、ジェイムソンの「パスティーシュ」論、ハッチオンの「パロディ」論などを参照することができる。Brenda R. SilverはVirginia Woolf Iconの中で、映画やポスターなどさまざまな媒体を通して「複製」され続けるウルフ像を問題として取り上げ、見る側が抱く不安や恐怖心について論じていたが、今回の『ダロウェイ夫人』の読み直しにおいても不安や恐怖心は重要な鍵となっている。しかし、その不安は後世の作家たちが先人に対して抱くものというより、『ダロウェイ夫人』のなかに描かれる危機感を通して、ポストモダンの作家が自分たちの不安を表現しているように思われる。
1960年代、70年代においてウルフが第二波フェミニズムやレズビアン批評家たちによって引き合いにだされることが多かったことは周知のとおりである。その理由の一つは、Laura Marcusも述べているように、ウルフの作品が彼女たちの主義・主張を代弁する役割を果たしていたからである。それに対して、21世紀において語り直される『ダロウェイ夫人』の場合はどうかと言えば、21世紀社会が抱える不安がウルフの作品を通して訴えられている。事実、作中人物の一人としてウルフを登場させているカニンガムは作家について「セクシュアリティがはっきりしない女性」として紹介するなど、ウルフの流動性、不安定性に注目していることが分かる。
本発表では、新しい世紀の転換期において『ダロウェイ夫人』に関係する作品が立て続けに出版されたということに注目して、どのような「書き直し」ないし「読み直し」が行われたのかを具体的に見ていく。そして、ウルフの『ダロウェイ夫人』を中心に拡散していく危機感の波紋についても考察していく。
ウルフとリチャードソン ――二人の前衛作家の映画への視線
青山学院大学准教授 大道 千穂
ウルフがエッセイ、「映画」(‘The Cinema’) を発表したのは1926年であった。興味深いことに、それはリチャードソンが前衛映画雑誌、『クローズ・アップ』に多数のエッセイを掲載していた時期とほぼ重なる。リチャードソンは1927年から33年までの6年間の間に、20を超えるエッセイを同誌に執筆・掲載した。アメリカで世界初のトーキー映画が上映されたのが1927年であることを考えると、二人が映画評を書いたのはサイレントからトーキーへと移っていく映画史上における重要な過渡期であったといえる。その誕生から芸術としての完成までを眼前で見たモダニズムの作家たち。映画が彼らに創作のインスピレーションを与えたとしても不思議ではない。本発表はウルフとリチャードソン、それぞれの映画に対する考え方や関心のあり方の違いを手掛かりに、意識の流れの手法を実践した前衛的な女性作家として一括りに考えられがちな二人の、小説家としての姿勢や手法の違いの一端を明らかにすることを目的としたい。
エッセイ「映画」において、ウルフは『カリガリ博士』の一シーンに偶然表れた影が言葉を超える雄弁さを持った例などを挙げ、今後、映画が芸術としてさらに成熟していく可能性に言及している。しかし同時に、映画がまだまだ他の芸術形態に寄生している未熟な段階にあることを述べ、今後の発展を深く憂慮している。一方のリチャードソンは、トーキー映画が普及するまでは映画という新しい芸術形態に対して徹底的にポジティヴであった。この温度差の大きな理由として、ウルフがあくまで映画の中身、その芸術性に関心を抱いていたのに対して、リチャードソンの関心は「何を見ているかよりも映画をみること」そのものにおかれていたことが挙げられるだろう。映画の普及により都市から農村、スラムに至るまでのすべての人々―性別、国籍、年齢を問わずすべての人々―が、等しく文明に触れられるようになったこと、語らない動く映像を熟視することで観客それぞれが自由に自分の物語を作って楽しめるようになったことを、リチャードソンは手放しで喜んでいる。ここには二人の作家の「物語」への姿勢の違いがよく表れている。ウルフが精巧に練られた構成と詩的な言葉で物語を紡ぎ、芸術的完成度の高い小説を読者に提供した一方で、リチャードソンはヒロイン・ミリアムの人生がただただ、延々と続く物語を世に出した。そこには考え抜かれたような構成もなく、読み手が読むためのガイドになる句読点すらも極端に少なかった。読者はリチャードソンの意図や影すらも感じることなく、直接ミリアムの意識の中に誘われ、ミリアムの意識に一体化し、ミリアムともに生きる。読み方が決まった、完成した物語の枠組みに作家が読者を押し込める従来の小説の在り方を「男性的」であるとして何よりも嫌ったリチャードソンは、読者は作者と同じだけの想像と創造の自由を与えられるべきであると考えたのだ。『遍歴』の文体、物語はこうして生まれた。彼女の映画評と比較しながら読んでみると、『遍歴』はセリフもなく、ただただ話が続いていくサイレント映画とよく似ている。
映画という観点から二人を比較していくうえでさらに面白いのは、トーキー映画普及以降の二人の映画に対する姿勢の相違である。サイレント期からトーキー期へと映画の主流が移っていく中で、徐々にサイレント映画こそが女性の領域であるという考え方を確立していくリチャードソンの映画評は、巻を追うごとにより深い沈黙へと向かっていく小説『遍歴』の物語の進行を理解する上でも興味深い。それでは短いセリフ、多くの行間、人間の不在、静けさが基調をなす『ジェイコブの部屋』を書いたウルフが、最後に多くの人、動物、物が織りなすさまざまな音が(不)協和音をなしながら進行するこの上なく騒がしい『幕間』を執筆するに至ったのもまた、映画から受けた何らかの影響があるのだろうか。残念ながらウルフはトーキー映画に関する映画評を書いていないが、この点についても考えてみたい。
第34回 日本ヴァージニア・ウルフ協会大会シンポジウム要旨
「メタモダニズム」とは何か
――現代文学とウルフそして/あるいはモダニズムの「継承」という問題
| 司会・講師 | 津田塾大学准教授 | 秦 邦生 |
| 講師 | 京都女子大学准教授 | 廣田 園子 |
| 講師 | 慶應義塾大学専任講師 | 近藤 康裕 |
| 講師 | 大阪大学准教授 | 山田 雄三 |
現代イギリスの小説家マギー・ギー(Maggie Gee, 1948- )が今年刊行した新作Virginia Woolf in Manhattanは、1941年に自ら命を絶ったはずのヴァージニア・ウルフが現代のニューヨークに復活するばかりか、イスタンブールで開催される国際ウルフ学会に乱入するという奇想天外な筋書きを持つ小説である。作品自体への評価は別として、20世紀前半のイギリスに生きたウルフを、現代アメリカならびにトルコへと「旅」をさせるこの小説の構想は、時間的・空間的領域を拡大してここしばらく活気づくモダニズム研究の現況を巧妙に寓意化していると言えるかもしれない。
Susan Stanford Friedmanの一連の論考や、Mark Wollaegerらが編纂したThe Oxford Handbook of Global Modernisms (2012)に代表される近年のモダニズム研究(いわゆる“New Modernist Studies”)は、かつてはウルフ、ジョイス、エリオットといった一握りの正典的作家を排他的に指示していた「モダニズム」という概念を拡張し、 ①空間軸を拡大して「グローバル・モダニズムズ」を語ろうとする欲望や、ときには②時間軸を延長して現代文学までモダニズムの一環として捉える見方すら提起している。研究の活況は歓迎すべきだが、では結局すべてがモダニズムなのだろうか? このようにして無際限に拡がるモダニズム研究の現代的意義とはなんだろうか?
本シンポジウムでは、そのようなモダニズム研究の自己省察の契機として、現代英語圏文学を検討する。“Metamodernism: Narratives of Continuity and Revolution” (PMLA 129.1 [January 2014])においてDavid JamesとUrmila Seshagiriは「メタモダニズム」という概念を導入し、20世紀後半から現代にかけての英語圏文学が、20世紀前半のモダニズム(ここでは「歴史的モダニズム」と呼称する)の「遺産」を「継承」するその様態を問題化している。メタモダニズムのフィクションは、①(冒頭で挙げた例のように)歴史的モダニズム作家を登場人物にしたり、作品に直接言及したりするもの、②戦間期の歴史的状況を暗示的/明示的主題とするもの、③モダニストの技法的革新に込められた倫理・政治意識を批判的に継承するものなど、さまざまな種類が考えられる。現在という地点を立脚点としつつ、ポストモダン的パスティーシュやのっぺりとしたインターテクスト性とも異なるかたちで、歴史的モダニズムの可能性と限界に対する真摯な応答をあらたな創作への糧とするメタモダニズムをひとつの鏡として置くことで、やはり現代において歴史的モダニズムの批判的「継承」をもくろむ学問的言説の現況を省察することができるのではないか――これが今回の企画の問いかけである。
“The Woman in the Book” ――編集者クラリッサの(ポスト)モダニティ
京都女子大学准教授 廣田 園子
マイケル・カニンガム (Michael Cunningham, 1952- ) の『めぐりあう時間たち』(The Hours, 1998) は、2002年の映画版の成功と相まって、現代におけるウルフ作品の最も有名な翻案例と言っても過言ではない。『ダロウェイ夫人』 (1925)を軸に時代も空間も異なる三人の女性の人生が交錯する本作の中から、本発表では1990年代のNYに生きるクラリッサ・ヴォーンに焦点を当てる。編集者として書物の生産者側に立つ一方、失敗に終わったリチャードの小説の主人公、“the woman in the book” でもある彼女は過剰なまでに文学に絡め取られた存在であり、自らが文学史上にその名を残す機会を逸したことを強く自覚しつつ、「現代版ミセス・ダロウェイ」としてテクスト中で機能する。現代作家によるモダニズム継承の議論において不可避的に問題となるポストモダニズムとの関連性を踏まえ、最も自己言及的なナラティヴとしてメタフィクショナルな要素を全面に押し出している彼女の一日を、カニンガムが如何にポストモダニズム的パロディとは異なる形で提示しているかを考察し、更にウルフ、カニンガム、そしてリチャードという三人の作家に異なる形で「支配」されるクラリッサの映画版における表象についても議論していきたい。
『贖罪』の倫理性と政治性 ――イアン・マキューアンのメタモダニズム
慶應義塾大学専任講師 近藤 康裕
現代作家がいかに20世紀前半の革新的な文学を継承/批判しつつ小説の創作を行なっているかに着目し、「メタモダニズム」という語を用いてモダニズムの再考に着手しているDavid JamesとUrmila Seshagiriは、イアン・マキューアン(Ian McEwan, 1948-)の『贖罪』(Atonement, 2001)を一例として挙げている。Jamesは、マキューアンのモダニズムに対するアンビヴァレントな態度を指摘しつつ、小説のあり方そのものを問う『贖罪』のメタフィクション性に、その「メタモダニズム」たる所以を読み込んでいる。ヴァージニア・ウルフに大きな影響を受けた主人公の文学実践が引き起こした悲劇を、彼女自身の小説の創作によって贖うという『贖罪』の構成それ自体が、モダニズムに対する批判的継承であると捉えられている。Jamesらは「メタモダニズム」の倫理的な側面と政治的な側面をともに強調しているが、『贖罪』の倫理的側面は文学実践をとおした贖罪という主題から前景化されるのに対して、その政治性は十分に議論されていない。本発表では、いわゆるモダニズムに対するマキューアンのアンビヴァレンスと『贖罪』の「メタモダニズム」の政治性について、モダニズムの歴史的意味の再検討を交えながら考察したい。
コロニアル・モダニティとその残滓 ――アミット・チョードリにおけるモダニズム、都市、記憶
津田塾大学准教授 秦 邦生
現代インドの英語作家アミット・チョードリ(Amit Chaudhuri, 1962- )は、サルマン・ラシュディ的なポストコロニアル文学のグローバリズムとの共犯性を繰り返し批判し、支配的な「ネイション」のナラティヴに代わる可能性を「歴史的モダニズム」の遺産に求めている。他方、チョードリによるモダニズムの系譜学は、ウルフ、ジョイス、ロレンスといった英文学の正典のみならず、19世紀に遡るベンガル地域の知識人たちの再評価を含み、コロニアル・モダニティの重層的歴史性を浮き彫りにする狙いを持っている。彼の小説・エッセイにおける都市空間――具体的には、かつてはイギリス帝国の第二の都市だったカルカッタ/コルカタ――表象にはその問題意識が集約されている。とりわけ、小説第三作Freedom Song (1998)や最近のエッセイCalcutta: Two Years in the City (2013)においては、日常性と断片的記憶を喚起するモダニズム的文体と、90年代以降の経済自由化によってグローバル化に曝される都市生活の現実とが奇妙に衝突している。本発表はこれらの作品を読み解くことで、(ウルフの特徴でもある)モダニズム的都市美学の現代インドへの転置が持ちうる批評的意味を考察したい。
モダニズム・フリンジの人称、時制、バイリンガリズム
大阪大学准教授 山田 雄三
私の報告では、モダニズム的批評意識、もしくはモダニズムのポリティックスが現代にどのように継承されているか、あるいは継承されそこなっているか問題提起をしてみたい。今ブームとなっている「モダニズム」の時間・空間的拡大は、21世紀における「モダニズム」のrevisionではけっしてなく、そもそも「モダニズム」に内包されていたvisionではなかったのかと。この問題を考える上で参考になるのは、ウェールズやスコットランドのモダニズム文学に見られる人称の扱いと、レイモンド・ウィリアムズが示した「想像力の時制」の扱いである。一方でメトロポリスにいないフリンジのモダニストたちは人称を操作することで、物象化・断片化に抗いながら共有される空間の形成を目指し、他方で、時制を操作することで、共有される未来への契機を探っていたように思える。そうした困難な試みと彼らの(ひいては私たちの)バイリンガル状況とを関連づけてみたい。