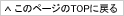2012年度
第32回全国大会 プログラム
| 日時 | 2012年11月18日(日)10:00~17:00 |
|---|---|
| 場所 | 関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス B号館104教室 〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号 http://www.kwansei.ac.jp/index.html |
| 交通 | ■阪急電鉄今津線 甲東園駅 下車 西宮北口行・関西学院行 関西学院前下車 バス約5分 西口 徒歩約12分 ■JR東海道線 西宮駅 下車 甲東園行 関西学院前下車 バス約15分 |
| 受 付 (9:30~10:00) | ||
| 開会の辞 (10:00) | ||
| 関西学院大学准教授 | 大 貫 隆 史 | |
| Ⅰ 研究発表(10:00~11:00) | ||
司会 |
岡山大学准教授 | 那 須 雅 子 |
| ダブリンという都市を移動するブルーム――『ユリシーズ』第6挿話「ハデス」を中心に | ||
| 東邦大学非常勤講師 | 高 橋 大 樹 | |
| ヴァージニア・ウルフの創造空間――ショートフィクションとエッセイにおけるハイブリッドな文学技法(レトリック) | ||
| 大阪成蹊大学教授 | 中 島 恵 子 | |
| Ⅱ ワーク・イン・プログレス報告(11:10~12:40) | ||
司会 |
東京学芸大学教授 | 大 田 信 良 |
| ジャズの受容とウルフ | 東京学芸大学特任講師 | 加 藤 めぐみ |
| 教育と文学 | 東洋大学専任講師 | 井 上 美 雪 |
| 成長と文学 | 一橋大学准教授 | 河 野 真太郎 |
| 開催校挨拶 (12:40) | ||
| 関西学院大学教授 | 田 村 和 彦 | |
| Ⅲ 総 会(14:00~14:20) | ||
司会 |
上智大学准教授 | 松 本 朗 |
| 会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他 | ||
| 東京家政大学教授 | 伊 藤 節 | |
| Ⅳ シンポジウム(14:20~17:00) | ||
| エリザベス・ボウエンのwartime novels/storiesを再考する | ||
司会・講師 |
神戸市看護大学教授 | 山根木 加名子 |
講師 |
岡山大学教授 | 剱 持 淑 |
講師 |
東京工業大学准教授 | 北 川 依 子 |
| 閉会の辞(17:00) | ||
会長 |
東京家政大学教授 | 伊 藤 節 |
| 懇 親 会 (17:20~19:20) | ||
会場関西学院会館(翼の間) |
||
| 会費6000円(学生 3500円) | ||
研究発表要旨
ダブリンという都市を移動するブルーム
『ユリシーズ』第6挿話「ハデス」を中心に
東邦大学非常勤講師 高橋 大樹
『ユリシーズ』第6挿話「ハデス」は、レオポルド・ブルームが友人ディグナムの葬儀に出席するため、ほかの出席者とともに馬車に乗り込む場面から描かれる。その後市内を移動し、埋葬が行われる墓地へと向かう。この挿話ではブルームが自ら歩いて目にするものというよりは、馬車の中から見える市内の様子が細部にわたって描かれるのはもちろん、ダブリンの街を歩き回るスティーヴン・ディーダラス、妻モリー・ブルームの浮気相手であるボイランの姿が描写される。しかし我々が忘れてはならないのは遊歩者としてのブルームの視点から多くのことが描かれる代わりに実際のダブリンの多くが排除されている可能性である。本発表では、都市を移動するキャラクターとしてのブルームが、ダブリンという都市において出会う人々との関係に着目し、さらにブルームの視点を通じてジョイスが一体どのような都市空間を構築しようとしていたのかを考えてみたい。
ヴァージニア・ウルフの創造空間
——ショートフィクションとエッセイにおけるハイブリッドな文学技法(レトリック)
大阪成蹊大学教授 中島 恵子
ヴァージニア・ウルフの短編とエッセイから、特に実験的技法による作品構築のメカニズムを含んでいる作品に注目し、“Modern Fiction” における「心に降りかかる無数の印象の雨」を捉えるというモダニスト宣言を実践した点を調べる。また“The Narrow Bridge of Art”でウルフが「将来書かれる小説、または小説の変種は、詩の属性のいくつかを身につけていることだろう。…… それは、調和しないものが奇妙に丸く固まったもの―現代人の心―という形をとるだろう。」と述べているように、ウルフの散文には、あらゆる文学形式が含まれている。Monday or Tuesdayから“Kew Gardens” “Mark on the Wall” をはじめとするいくつかの作品とessay-fictionとも読める“The Death of the Moth”などハイブリッドな手法で描かれているものを例に、短いスケッチとしての短編とエッセイが凝縮された形でウルフのレトリックを示している点と、それらが素材としてMrs. DallowayやBetween the Actsなどの長編に生かされていく点に注目し、ウルフの創造空間における実験技法とヴィジョンを探る。
ワーク・イン・プログレス報告要旨
ジャズの受容とウルフ
東京学芸大学特任講師 加藤 めぐみ
衰退する大英帝国に代わって、世界の覇者となった<帝国アメリカ>。覇権の移行期である20世紀前半、英国人はアメリカ文化——ジャズ、フォード車、ハリウッド映画——をどのように受容したのだろうか。本発表ではアメリカの大衆文化に対する英国人の受け止め方を単に文化史的に辿るのではなく、Abravanelの議論をふまえて、英国人がアメリカ文化との関係を通して自国の文化をどのように再構築していき、またその再構築によって英国のモダニズム文学がいかに発展、変化を遂げたかを「ジャズの受容とウルフ」に照準を絞って紹介していきたい。
<参考文献>
Genevieve Abravanel, Americanizing Britain: The Rise of Modernism in the Age of the Entertainment Empire (Oxford and NY: Oxford UP, 2012)
教育と文学
東洋大学専任講師 井上 美雪
近年のウルフ研究は、イングランドの田舎や都市のなかに帝国の表象をとらえ、どのように国家が作り上げられてきたのかを明らかにしてきた。その過程で、例えばSuzanne Lynch(2007)は、”The novel [The Years] explore the different ways in which nations are imagined, constructed, and represented”と述べている。ところで、この引用冒頭の”The novel”を「教育」に置換することは可能である。つまり、教育もイングランドの在り方を照射するものなのである。本発表では、文学作品に描かれた教育の表象を探ることで、そこに生きる人々の中に刻印されている帝国のありようを見出してみたい。具体的には、Report of the Consultative Committee on the Primary School (1931)や教員の手引書であるHandbook of Suggestions(1927, 1937)等の一次資料、およびCCCSによるUnpopular Education(1980)等を参考に、The Yearsを読み解きたい。
成長と文学
一橋大学准教授 河野 真太郎
本報告では、文化と社会の全体を考える糸口として「成長と文学」という切り口を提案したい。教養小説や、非常に現代的で個人化された「成長」の観念を超えて、またもういっぽうでたとえば「経済成長」と言うときの「成長」の意味を、またはそれにまつわる経験を排除しない形で、より広く「成長」を考えるにはどのようなアプローチがあり得るのか。その足がかりとして、Jed Esty, Unseasonable Youth: Modernism, Colonialism, and the Fiction of Development (Oxford UP, 2012)を紹介する。最終的にはこの本で意図的に排除されているかに見えるRaymond Williamsの著作を検討することで、この本の批判的な検討もできればよいと思っている。
第32回日本ヴァージニア・ウルフ協会大会シンポジウム要旨
エリザベス・ボウエンのwartime novels/storiesを再考する
| 司会・講師 | 神戸市看護大学教授 | 山根木 加名子 |
| 講師 | 岡山大学教授 | 剱持 淑 |
| 講師 | 東京工業大学准教授 | 北川 依子 |
これまで正当な評価を得られなかったボウエン文学は、ボウエン(1899-1973)生誕100周年となる1999年前後から再評価され始めた。その理由は現代文学地図における女性作家の「場」の見直しにあるとして、モード・エルマンはこう述べる。「20世紀小説の評論におけるジョイス的モダニズムの支配により、その作品が古典的リアリズムとモダニスト的実験主義との境界線上をさ迷うようなボウエン、レベッカ・ウエスト、アイヴィ・コンプトンバーネットといった作家の業績は影が薄い。(だが)彼女らは、はっきりとは定義できないやり方で革新的であり、現代の文学上の革新は盛期モダニズム(high modernism)の主に男のストーリーには限定されえないことを示している」(Elizabeth Bowen序文)。
では、ボウエンにおいて明確に定義しがたいやり方で表現される革新性、モダニティとは何か。シンポジウムでは、「戦争」に関わる長短編を中心に読むことによりこの答えを探りたい。二度の世界大戦を生き抜いたボウエンにとって、戦争とはまず世界大戦を意味するが、同時に、アングロ・アイリッシュ作家としてアイルランドにおける対英独立戦争(1919-1921)をも意味している。
今回、主に取り上げるのは、戦間期から1940年代頃までに書かれたボウエンの短編、第二次大戦下のロンドンを舞台に展開する『日ざかり』(The Heat of the Day, 1949)、1920年の対英抗争当時のアイルランドを舞台とする『最後の九月』(The Last September, 1929)である。ウルフの『幕間』(1941)との比較を交えたり、また、同時代のモダニスト作家、ヘンリー・グリーンにも言及する予定である。
エリザベス・ボウエンのミステリアスな短編と世界大戦
岡山大学教授 剱持 淑
20世紀は二つの世界大戦の悪夢をみた時代であるとともに、人間心理への関心の高まりをみせた時代でもある。エリザベス・ボウエンの短編には、戦争の時代という歴史的時間を生きる女性登場人物が、正体不明の力にとらわれて闇の奥に連れ去られる(もしくは、連れ去られたかに見える)、過去から現在までの心理的時間を描く物語もあれば、パートナーのおかげで呪縛の罠にとらわれずこちらの世界に戻ってくる物語もある。日常生活の一場面のように始まりながら、無意識のうちに戦争や喪失や死の恐怖にとらわれた(もしくはその破壊力に魅せられた)登場人物の意識を描く叙述の特徴に着目してボウエンの短編を読みなおしてみたい。主に戦間期から1940年代頃までに書かれた短編の中から、「猫が跳ぶとき」(The Cat Jumps, 1934)、「あの薔薇を見てよ」(Look at All Those Roses, 1941)、 「幸せな秋の野原」(The Happy Autumn Fields, 1944)、「悪魔の恋人」(The Demon Lover, 1945)などのミステリアスな作品を取り上げる。
参考文献
・Bowen, Elizabeth. The Collected Stories of Elizabeth Bowen. New York: Anchor Books, 2006.
・Corcoran, Neil. Elizabeth Bowen: The Enforced Return. 2004. Oxford: Oxford UP, 2008.
・山根木加名子『エリザベス・ボウエン研究』旺史社、1991年.
祖国の不在————『日ざかり』と第二次世界大戦
東京工業大学准教授 北川 依子
エリザベス・ボウエンの『日ざかり』 (The Heat of the Day, 1949) は、第二次大戦下の英国の空気を鮮やかに再現した小説として、高い評価を得てきた。スパイ小説の枠組みを巧みに用いたこの作品は、ヒロインの恋人がナチスのスパイであるという疑惑を軸に展開する。その根底にあるのは、忠誠とは、祖国とは、ひいては国家とはなにかという、大きな問いである。
第二次大戦期の英国において、個人と国家の関係を中心に据えた小説は数多く見られる。それらと比較したとき、ボウエンを特徴づける要素としてまず浮かび上がるのは、アングロ・アイリッシュという出自であろう。第二次大戦を通して、アイルランドは中立政策を保った。二つの国の板挟みになったボウエンは、みずから申し出てアイルランドにおける政治状況を調査し、英国情報省へ報告をおこなった。この経験は、もとより不安定であった彼女の帰属意識の基盤を、さらに揺るがしたものと思われる。
『日ざかり』はナショナリティをめぐる問題をどのように描いているのか。第二次大戦を扱う同時代の作品と対比したとき、そこにはどのような類似、相違が見出せるのか。ウルフの『幕間』やヘンリー・グリーンの小説も考察の対象としつつ、ボウエンの作品を読みなおしてみたい。
参考文献
・Corcoran, Neil. Elizabeth Bowen: The Enforced Return. Oxford: Oxford UP, 2004.
・MacKay, Marina. Modernism and World War II. Cambridge: Cambridge UP, 2007.
・Mengham, Rod and N. H. Reeve, eds. The Fiction of the 1940s: Stories of Survival. Basingstoke: Palgrave, 2001.
『最後の九月』を読む——ダニエルズタウンを表象として
神戸市看護大学教授 山根木 加名子
『最後の九月』(The Last September, 1929)では、1920年、対英独立戦争に揺れる南アイルランド、コークのネイラー家の館「ダニエルズタウン」を舞台に、ネイラー卿の姪でここに寄宿する19歳のロイスの「成人女性とは」(sexual identity)、「国家とは」(national identity)という探求テーマが展開する。ダニエルズタウンはビッグ・ハウスと総称されるアングロ・アイリッシュ・プロテスタント支配階級の所領の一つだが、作品の最後でアイルランド民族独立主義者の焼き打ちにより炎上する。同様なビッグ・ハウス炎上(または破壊)シーンは、ウィリアム・トレヴァーの『運命の愚者』(Fools of Fortune, 1983)やジョン・ バンヴィルの『バーチウッド』(Birchwood, 1973)にも登場する。
そこで、これらの作品との比較も交えて、ダニエルズタウンという空間や炎上の表象的意味を解読しつつ、歴史的コンテクストとロイスの探求がどう交錯していくか考察する。あわせて、作品に見られるモダニズムとは何かを明らかにしたい。また、オープン・エンディングで示されるロイスの未来を探るために『日ざかり』(1949)にも言及する。
参考文献
・Ellmann, Maud. Elizabeth Bowen: The Shadow Across the Page. Edinburgh: Edinburgh UP, 2003.
・Esty, Jed. “Virgins of Empire: The Last September and the Antidevelopmental Plot.” Modern Fiction Studies 53.2 (2007): 257-75.
・Walshe, Eibhear, ed. Elizabeth Bowen. Dublin: Irish Academic P, 2009.