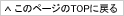2011年度
第31回全国大会 プログラム
| 日時 | 2011年10月30日(日)10:00~17:20 |
|---|---|
| 場所 | 一橋大学 国立西キャンパス 本館26番教室 〒186-8601 東京都国立市中2-1 http://www.hit-u.ac.jp/index.html |
| 交通 | ■JR中央線 国立駅 下車 南口 徒歩約6分 ■JR南武線 谷保駅 下車 北口 徒歩約20分 国立駅行 一橋大学下車 バス約6分 |
| 受 付 (9:30~10:00) | ||
| 開会の辞 (10:00) | ||
| 都留文科大学教授 | 窪 田 憲 子 | |
| Ⅰ 研究発表(10:00~12:10) | ||
司会 |
都留文科大学教授 | 窪 田 憲 子 |
| 『オーランドー――ある伝記』における同時代の詩(人)・過去の偉大な詩(人)・売れる詩(人)の錯綜 | ||
| 青山学院大学大学院生 | 四 戸 慶 介 | |
| ティビー・シュレーゲルと『ハワーズ・エンド』――ダンディズムに生きた世代の葛藤 | ||
| 上智大学大学院生 | 中 村 美帆子 | |
司会 |
津田塾大学専任講師 | 秦 邦 生 |
| マーティン・パージターとピーター・パンの場合――エドワード朝期におけるモダニズム、帝国主義、リベラリズム | ||
| 一橋大学大学院生 | 高 田 英 和 | |
| 「匿名性」という戦略――オメガ工房におけるロジャー・フライの狙い | ||
| 三菱一号館美術館学芸員 | 加 藤 明 子 | |
| Ⅱ 総 会(13:40~14:00) | ||
司会 |
東京学芸大学教授 | 大 田 信 良 |
| ・会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他 | ||
| 東京家政大学教授 | 伊 藤 節 | |
| Ⅲ シンポジウム(14:10~17:20) | ||
| 1930年代、ヴァージニア・ウルフの<同時代人>たち――<連帯>あるいはコスモポリタニズムの時間性 | ||
司会 |
成蹊大学教授 | 遠 藤 不比人 |
講師 |
香川高専准教授 | 市 川 緑 |
講師 |
一橋大学教授 | 中 井 亜佐子 |
講師 |
早稲田大学非常勤講師 | 三 宅 美千代 |
| 閉会の辞(17:20) | ||
会長 |
東京家政大学教授 | 伊 藤 節 |
| 懇親会(18:00~20:00) | ||
会場リストランテ国立文流 |
||
| 会費6000円(学生 3500円) | ||
研究発表要旨
『オーランドー――ある伝記』における同時代の詩(人)・過去の偉大な詩(人)・売れる詩(人)の錯綜
青山学院大学大学院生 四戸 慶介
商業的な成功を収めた『オーランドー-ある伝記-』は、同時代作家を認めない著名な批評家ニコラス・グリーンの仲介で売れる詩人となるオーランドーの伝記を描く。近年P. Collier、E. W. Gordon、J. Dubino 等によって出版市場・文化に焦点を当てたモダニスト・ウルフの文化生産性と商業性・国際性との関連が見直されている。本発表ではそれに付け加える形で、ニューボルト・レポート、大学教育における英文学カリキュラム編成等、国文学の制度化との関わりを検証する。圧縮したイギリス史に、同時代の交錯する商業・芸術・国文学の言説を自己批判的にパロディ化した、ウルフの国文学再考への態度を考察する。
ティビー・シュレーゲルと『ハワーズ・エンド』――ダンディズムに生きた世代の葛藤
上智大学大学院生 中村 美帆子
E. M. フォースターの『ハワーズ・エンド』(1910)について、帝国主義下を生きたダンディズムの世代に着目して考察する。主人公マーガレットの弟ティビー・シュレーゲルは、帝国主義や家父長としての支配に携わることを拒否するが、その姿勢はマーティン・グリーンがChildren of the Sun (1976)で示す「太陽の子どもたち」を想起させる。この第一次大戦後の英国社会に多大な影響を及ぼしたとされる知的階級出身の若者たちは、ヴィクトリア朝的な男性権力を受け継ぐことを拒絶し、ダンディズムに傾倒することで新たな立場を模索した。本発表では、こうした若者世代とティビーとの関連を分析し、帝国主義下の知識人たちの葛藤を明らかにする。
マーティン・パージターとピーター・パンの場合――エドワード朝期におけるモダニズム、帝国主義、リベラリズム
一橋大学大学院生 高田 英和
本発表は、ウルフの「ベネット氏とブラウン夫人」を手がかりにして、エドワード朝期における人間の生/性の変化を、この時期の大英帝国の内向きへの変容との関係から考察する。取り上げる作品は、ウルフの『歳月』、バリの『ピーター・パン』である。結婚の不在に着目しながら、二作品に共通する、新たな「成長」概念、もしくは、「成長概念」の不在を、帝国主義の終焉とリベラルな国民国家観の誕生というメタナラティヴの中に位置付けて行きたい。ウルフとバリが提示する、大人の男への成長の拒否、つまり、幼児性の称揚という問題が、この時期における「児童文学」の興隆と「モダニズム」の出現と密接な関係にあることを明らかにしたい。
「匿名性」という戦略――オメガ工房におけるロジャー・フライの狙い
三菱一号館美術館学芸員 加藤 明子
1913年、ロジャー・フライは「生気あふれる独創的な」応用芸術をめざして「オメガ工房」を開設した。このロンドンを拠点とした活動については、従来アーツ・アンド・クラフツ運動や近代デザイン運動の亜流と見なされることが多く、独自の意義が明確にされなかった。しかし、参加者に職人技術の習得を求めず、未経験者との共同作業を奨励し、いびつで荒削りな仕上げをあえて追求するなど、その制作方針の特異さはきわだっている。したがって、この芸術運動を正しく理解するには、構想の原点にまで立ち戻る必要がある。本発表では、「匿名での」共同制作という約束事が孕んでいた問題点とフライの意図とを精査して、構想の解明に結びつけたい。
第31回日本ヴァージニア・ウルフ協会大会シンポジウム要旨
1930年代、ヴァージニア・ウルフの<同時代人>たち
――<連帯>あるいはコスモポリタニズムの時間性
| 司会 | 成蹊大学教授 | 遠藤 不比人 |
| 講師 | 香川高専准教授 | 市川 緑 |
| 講師 | 一橋大学教授 | 中井 亜佐子 |
| 講師 | 早稲田大学非常勤講師 | 三宅 美千代 |
モダニズム論が、ポストコロニアル批評が、あるいは、その後の「帝国」をめぐる議論が制度化してしまった後で、文化/文学批評はなにを語れるのか? この設問が含意してしまうのは、批評理論なるものが不断の「進化」を遂げるべきであるという、一種19世紀風の進歩史観であるのかもしれない。この時間性と連動するのが、言及する地名をイングランドのみならず大西洋を越えてカリブへ、あるいはアフリカへと拡大すべきであるといった空間的認識で、ここでは批評理論の「進化」という直線的時間性が空間の「拡大」というそれ自体「帝国」的な地政学的(無)意識と共鳴し合っていないだろうか(ここに中心と周縁といった空間性を指摘してもいいだろう)。本シムポジウムでは、この「進化=拡大」といった無意識の「帝国」的な時間性=空間性が見逃してきたかもしれぬ「同時性」ということに注目してみたい。1930年代のロンドンで、ウルフとC・L・R・ジェイムズが同時にマルクスを引用し、ユナ・マーソン(Una Marson)がブラック・ブリティッシュ・フェミストとして活躍する、この同時性と現代のセネガルの映画監督センベーヌ・ウスマン(Sembène Ousmane)が過去に読み解くブラック・アトランティックな「連帯」を併置するとき、なにが見えてくるのか。つまり「現在」が「過去」の中に読む「未来=連帯」の可能性=同時性ということ。このような同時性から批評理論なる言説の無意識の「帝国」性へ介入を試みるとき、ウルフの1930年代のフェミニズムに今現在どのような「未来=連帯」の可能性=同時性(アクチュアリティ)が見えてくるだろうか?
(文責:遠藤不比人)
歴史を書くこと、未来を語ること――ウルフ、C・L・R・ジェイムズ、祖国無き者たちの連帯
一橋大学教授 中井 亜佐子
『三ギニー』と『ブラック・ジャコバン』――前者はフェミニズム、後者は黒人思想の古典として知られるテクストだが、実は、同じ年(1938年)に刊行されている。両者はいずれも、マルクスの歴史記述とマニフェストの形式(『共産党宣言』と『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』)を1930年代の文脈に再演するテクストでもある。
当時トロツキストとして英国で活動していたC・L・R・ジェイムズは、ハイチ革命 (1791-1804年)をフランス革命の完成形としてのプロレタリア革命と位置づける一方、トゥサン・ルヴェルチュールの人間的な悲劇――フランス革命の普遍的理念を追い求め、「大衆」の「人種感情」と乖離していく指導者の悲劇――としても描く。革命の悲劇性の認識を通じて、ジェイムズは逆説的にも、20世紀の植民地独立闘争の世界的な連帯を構想するに至る。ジェイムズの語る「未来」は、ウルフの「アウトサイダー協会」のヴィジョンにも通じるのではないか。ジェイムズとウルフの同時代性を意識し、二つのテクストを重ね合わせることによって、そこに共有される反時代的な提言を読み取ることが、本発表の狙いである。
1930年代ロンドン――Una MarsonとWoolfはすれ違っていたのだろうか
香川高専准教授 市川 緑
ユナ・マーソン(Una Marson, 1905-1965)は、モダニズム期のイギリスで多彩な活動を見せた、先駆的なカリブ出身ブラック・ブリティッシュ・フェミニストとしてこのところ着目されてきている。彼女は1932年から36年と、1938年から46年の間、ロンドンに滞在して、詩や劇や雑誌記事を書きながら国際的フェミニストや黒人の運動団体で中心的な役割を担い、またBBCのプロデューサーとしてラジオを媒体にカリブ文学を世に出す一助も果たした。本発表では、ナショナリティ、人種、ジェンダー、階級の問題がクロスし流動する現場で生み出されたマーソンのテクストを、彼女の詩にみられるcultureの痕跡である「本歌取り」にも注目しながら読んでみたい。さらにそれをウルフのフェミニズム・国民文化論と併置したときに、二方向からの言説は相互交渉的な関係を結びうるのか、考察したい。
植民地兵の憂鬱——センベーヌ・ウスマン『キャンプ・チャロエ』におけるブラック・アトランティックな連帯
早稲田大学非常勤講師 三宅 美千代
セネガルの映画監督センベーヌ・ウスマン(Sembène Ousmane, 1923-2007)は、アフリカ人の視点に立脚した映画製作を志した。『エミタイ』(Emitai, 1971)と『キャンプ・チャロエ』(Camp de Thiaroye, 1988)は、第二次世界大戦を扱った作品だが、いずれも歴史上の事件を題材に、フランス植民地のブラック・アフリカ各国に強いられた強制徴用と抑圧を物語の主軸に据えることで、欧米中心主義的な歴史記述に抵抗するものである。
センベーヌ自身、フランス軍に従軍した経歴を持つが、そこで経験した差別や連合軍兵士たちとの出会いが、植民地問題に目覚めるきっかけを与えたと語る。大戦末期に起こったフランス軍隊によるセネガル兵士虐殺事件を題材とする『キャンプ・チャロエ』では、米軍黒人兵とセネガル兵の友情が描かれ、ラングストン・ヒューズ、マーカス・ガーベイらの名前がでてくる重要な場面がある。この作品で示唆される、ブラック・アトランティックな連帯の可能性が、映像を通して歴史を語る行為に対し、どのように介入しうるのか考察する。