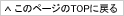2009年度
第29回全国大会 プログラム
| 日時 | 2009年11月7日(土)10:30~16:45 |
|---|---|
| 場所 | 明治大学・和泉キャンパス メディア棟306番教室(3階) 〒168-8555 東京都杉並区永福1-9-1 http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/ http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/izumi/access.html |
| 交通 | ■京王線 / 新宿駅から特急1つ目(約6分)、急行(通勤快速・快速)2つ目(約7分) ■都営新宿線(京王新線直通)/快速(橋本行)新宿→笹塚→明大前 (新宿から約10分) ■井の頭線 / 渋谷から急行2つ目(約7分) 吉祥寺から急行3つ目(約13分) 明大前駅より徒歩5分 |
| 受 付 (10:00~10:30) | ||
| 開会の辞 (10:30) | ||
| 広島市立大学教授 | 土井 悠子 | |
| Ⅰ 研究発表(10:30~12:00) | ||
司会 |
広島市立大学教授 | 土井 悠子 |
| ・Orlandoにみる帰属の曖昧さ――公的領域と私的領域の往還 | ||
| 東京慈恵会医科大学非常勤講師 | 木下 未果子 | |
| ・『波』のなかのシンボルたち | ||
| 元佛教大学教授 | 川野 美智子 | |
司会 |
東京学芸大学教授 | 大田 信良 |
| ・画家の絵筆は踊る――『灯台へ』における視覚の現象学 | ||
| お茶の水女子大学非常勤講師 | 浦野 郁 | |
| Ⅱ 総 会(13:30~13:45) | ||
司会 |
帝京大学教授 | 高井 宏子 |
| ・会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他 | ||
| 神戸市外国語大学教授 | 御輿 哲也 | |
| Ⅲ シンポジウム(13:45~16:45) | ||
| Theatricality/Anti-theatricalityとウルフ | ||
司会 |
早稲田大学専任講師 | 吉野 亜矢子 |
講師 |
東京工業大学非常勤講師 | 近藤 章子 |
講師 |
東京理科大学非常勤講師 | 吉田 えりか |
講師 |
早稲田大学助手 | 内田 夕津 |
| 閉会の辞(16:45) | ||
会長 |
神戸市外国語大学教授 | 御輿 哲也 |
| 懇親会(17:30~20:00) | ||
会場Taverna Bacca(電話 03-3325-8801) 明大前駅より徒歩1分 |
||
会費6000円(学生 3500円) |
||
Orlandoにみる帰属の曖昧さ――公的領域と私的領域の往還――
東京慈恵会医科大学非常勤講師 木下 未果子
Orlando: A Biography (1928) において、300年以上の年月を経た後、Orlandoに漸く詩を完成させた契機は何であったのか。この点について、公共性論および親密圏論を軸にして論考する。Orlandoは生涯を通じ、性別・階級・職種・血統などの規制枠を超越し、帰属は終始曖昧であった。その曖昧性ゆえに、彼/彼女の人生は、公的/私的の両領域を自由自在に往還するが、どちらの領域もさまざまな形で彼/彼女に制約を課し、生涯の課題であった詩作の進行を阻んだ。最終的に、ジェンダーの曖昧な特異な結婚によって、新たな領域が構築され、創作活動への障害が排除されて、詩は完成する。この新領域の特色を近年公共性論に関連して注目される親密圏と重ねて考察し、WoolfがOrlandoに託した創作環境の確立への展望を探る。
『波』のなかのシンボルたち
元仏教大学教授 川野 美智子
長篇第六作の『波』は、それ以前の小説に内包される求心的な時間の美学の最高峰を示している。この時期以後『オーランドウ』、『三ギニー』やエッセイなどを通して歴史的・社会的関心が高められていったが、『波』はひたすら個人の内面に生成・蓄積されていく人生の意義を追い求める。この文学的技法の最も特徴的なものとして、九つのプロローグとエピソードから成る構成の特異性があるが、私はすべてのエピソードを覆う「海」の象徴の下に、ウルフが駆使したシンボルとして「鰭、エルブドン、パーシヴァル、馬、卵の殻」を挙げたい。そのすべてが、彼女が渾身の力をこめて追究した青春と美、過ぎ行く時と死の意味を証するものであると考える。
画家の絵筆は踊る――『灯台へ』における視覚の現象学
お茶の水女子大学非常勤講師 浦野 郁
『灯台へ』第3部において、リリー・ブリスコウは一枚の絵画を速やかに完成させているが、第1部での困難な創作活動に比べ、ここで彼女の身体の軽やかな動きが注視されていることは注目に値する。本論は、モーリス・メルロ=ポンティの著作から、特に視覚及び絵画について書かれたものを援用することで、リリーの絵画制作に見られる視覚の身体性の意義を考えるものである。メルロ=ポンティは、我々が目にする世界とは第一に身体の可動性がもたらすものであるとし、「眼は精神に連なるもの」という伝統的な視覚観に異を唱えたが、これを例証できる稀有な存在として画家を挙げている。このメルロ=ポンティの考え方を下敷きに、第3部でのリリーの創作が、第1部において男性たちがラムジー夫人に向ける眼差しに対し、いかに有効な抵抗となり得ているかを検証したい。
第29回日本ヴァージニア・ウルフ協会大会シンポジウム要旨
Theatricality/Anti-theatricalityとウルフ
| 司会 | 早稲田大学専任講師 吉野亜矢子 |
| 講師 | 東京工業大学非常勤講師 近藤 章子 |
| 講師 | 東京理科大学非常勤講師 吉田えりか |
| 講師 | 早稲田大学助手 内田 夕津 |
TheatricalityとAnti-theatricalityは、社会と芸術の双方をまたぐ重要な概念である。同時に、双方がお互いの反対を意味しない、という意味で不均衡なタームでもある。OEDによれば “Theatricality”という語は1837年にトーマス・カーライルによって作られた。”theatrical”という語の成立から、100年近くを経て誕生したこの語は、造語者、カーライルによっては、何よりもまず市民社会の参加条件と位置づけられている。「演劇性」とも「劇場性」とも訳され、18世紀から19世紀にかけての民主主義の理念が発達していく上で重要な役割を果たしていたのだと指摘する研究者もいる。
ひるがえってanti-theatricalityは劇場性ないしは演劇性の欠如ではなく、演劇的なるもの、劇場的なるものへの反感や嫌悪を意味する。ジョナス・バリッシュは1981年に、著書The Antitheatrical Prejudiceにおいて西洋史を通して見られる演劇に対する反感を指摘し、特に19世紀小説とanti-theatricalityとの関係を読む一連の研究に道を開いた。2006年に出版されたアラン・アッカーマンらによる論文集Against Theatreは、バリッシュの論を批判的に展開し、ウルフと同時代のモダニズム演劇が見せた意識的なanti-theatricalityの諸相をつまびらかにしている。
とすれば、いくつかの問題群が浮かび上がるだろう。ウルフにとって、theatricalityとはなんだったのか。また、バリッシュの語るような19世紀的なanti-theatricalityや、アッカーマンらがモダニズム演劇にみたような意識的なanti-theatricalityを持っていたのだろうか。Theatricalであることと、社会とのかかわりをウルフは一体どのような観点から捉えていたのだろうか。
本シンポジウムは、theatricality/ anti-theatricalityをキーワードに、刻々と変化しつつあった当時の演劇、社会とウルフとのかかわりを検討する。
ウルフの小説に見られる(反)演劇性―
『フラッシュ』と『ウィンポール街のバレット家』
東京工業大学非常勤講師 近藤 章子
多くのモダニズム作家が演劇という表現形式へと向かい、それまでの演劇の概念に対する抵抗を試みたように、ウルフもまた戯曲『フレッシュウォーター』(1923, 1935)と、『幕間』(1941)における野外劇という形で劇作品を残している。しかし、あくまでも作品の中で上演される劇である後者は言うに及ばず、前者も仲間内での余興のために書かれたいわば私的な作品であり、公的な場での上演を念頭に置いた劇ではない。演劇に並々ならぬ関心を持ち、観劇を楽しんだウルフがとったこのような姿勢はモダニズムの反演劇性のひとつの表れといえるだろう。それは、台詞とト書きから構成される演劇形式を取り入れていない他の作品にも見出される。
『幕間』以外の作品における演劇的要素については様々な視点から論じられてきたが、今回は近年注目されつつあるものの、これまで軽視される傾向があった『フラッシュ』(1933)を取り上げる。ルドルフ・ベシエの喜劇『ウィンポール街のバレット家』(1930)が『フラッシュ』の執筆に影響を与えたことはよく知られているが、従来の批評ではこの劇に全く言及しないか、先行作品としての意義を指摘するかのいずれかであった。本発表では、ウルフがいかに演劇を意識し、また同時に演劇性の持つ側面に批判的な視線を向けているかを考察する。それによって、『フラッシュ』が『歳月』(1937)以降の後期作品の先触れとしての重要性を持つことを見ていきたい。
ヴァージニア・ウルフの『フレッシュウォーター』における反演劇性
東京理科大学非常勤講師 吉田 えりか
ヴァージニア・ウルフ唯一の戯曲『フレッシュウォーター』は、『ダロウェイ夫人』執筆中の気晴らしとして書き始められ、1923年に上演予定だったが、大幅な書き直しを経て、1935年にようやく上演された。1923年に一旦書き上げられた原稿と、上演に使ったと考えられる二つのテクストにはかなりの差異が認められ、中でも、女優エレン・テリーの、劇中での扱いの違いが目立っている。
ウルフの演劇に関するエッセイや劇評には、大仰な演技への嫌悪という意味での反演劇的嗜好は見られるものの、『フレッシュウォーター』自体に、特に新奇なモダニスト的試みは見られないように思われる。しかしながら、Alan AckermanらがAgainst Theatreの序において論じるように、観客と演技者、また、劇場と外の世界とを隔てる境界線をなくそうとする動きを、モダニズムにおける反演劇的動きであるとすれば、『フレッシュウォーター』のテクストにもその演出においても、反演劇的と考えられる要素が認められる。本発表では、その要素について考察すると共に、テクストの差異に、ウルフの反演劇的思考が影響を与えているかどうか、エレン・テリーに焦点を当てて考察していきたい。
“The Cinema”のアメリカにおける受容-
アンチ・シアトリカリズムの視点から
早稲田大学助手 内田 夕津
ヴァージニア・ウルフの “The Cinema”(1926)は同時期に少なくとも3誌、さらに1954年にも1誌に掲載されるほど注目されたエッセイである。中でも “The Cinema” が “The Movies and Reality”と改題され掲載されたThe New Republic誌においては、編集者のギルバート・セルデス自らが“The Abstract Movie”を寄稿してウルフに応答するほど、重要視された。セルデスは、映画を芸術として認知した第一人者でありAlan Ackermanが論じるように、モダニズム期のアメリカにおけるアンチ・シアトリカリズムの旗手である。映画が芸術として確立されるためには、シアターの影響から独立することが重要であると主張した批評家であった。
本発表では、The New Republic誌に掲載された上記二編のエッセイの「応答」を分析し、アンチ・シアトリカリズムの旗手がウルフの映画論に何を見出だし、何を無視したのかを論じる。“The Movies and Reality” においてウルフは映画が持つ可能性を認めつつ、その危険性を危惧しているが、セルデスが注目したのはシアターとは異なる映画の特質―後に彼がシアターからの映画の独立を提唱する際に提示する特質―をウルフが察知し、映画の未来の形を論じている点であった。本発表では特に“The Abstract Movie”の冒頭に提示された“The Movies and Reality”からの引用箇所に注目し、ウルフの映画論と後に展開されるセルデスのアンチ・シアトリカリズムとの間に呼応が見られることを、セルデス著のAn Hour with the Movies and the Talkies(1929)の分析を通して論じたい。