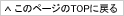2006年度
第26回大会
| 日時 | 2006年11月4日(土) 10:00~17:00 |
|---|---|
| 場所 | 金沢学院大学 2号館 〒920-1392 金沢市末町10 TEL 076-229-1181(代)Fax: 076-229-8995 |
| 交通 | JR金沢駅より直通バスで40分 東口 10番乗り場 18番系統 「本多町経由金沢学院大学行き」 西口 4番乗り場 11番系統「橋場町経由金沢学院大学行き」 5番乗り場 10番系統「香林坊経由金沢学院大学行き」 |
受 付 (9:30~10:00)
開会の辞(10:00)
いわき明星大学学長 高重 正明
Ⅰ 研究発表(10:00~12:10)
司会 広島市立大学助教授 土井 悠子
- 散文詩と『波』についてs
上智大学大学院生 小室 龍之介 - 理解できない歌の美しさ
― ヴァージニア・ウルフ、ヘンリー・グリーンと、1930年代のロンドン
山脇学園短期大学非常勤講師 中川 千帆
司会 神戸市外国語大学教授 御輿 哲也
- Virginia Woolfと Jean Rhysの比較考察
― 母子関係を中心に
青山学院大学非常勤講師 佐竹 由帆 - ユートピア/ディストピア?
―『オーランドー』における生殖のポリティクス
東京学芸大学非常勤講師 加藤 めぐみ
Ⅱ 開催校挨拶(13:10)
金沢学院大学文学部長 柳澤 良一
Ⅲ 総会(13:20~13:40)
司会 同志社大学助教授 山本 妙
会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他
Ⅳ シンポジウム(13:50~17:00)
感受するモダニズム―音楽、映画、シェルショック
| 司会・講師 | 慶応義塾大学講師(有期) 佐藤 元状 |
| 講師 | 早稲田大学客員講師 吉野 亜矢子 |
| 講師 | エクセター大学大学院生 矢口 朱美 |
閉会の辞 (17:00)
会長 都留文科大学教授 窪田 憲子
散文詩と『波』について
上智大学大学院生 小室 龍之介
ウルフの『波』で用いられる散文詩という形式は、音楽性への強い意識が働いた結果の文体であるが、『波』というテクスト内にもその音楽性を連想させる語彙に満ちていることから、『波』が捉える世界も音楽性に満ちているという考察も可能であろう。
だが、先行研究に見られるような「音楽性」という概念のレベルは、「音」もしくは「音響」というレベルに比べて限定的にならざるを得ない。「音楽」とは極めて美的な対象だが、「音」というレベルでは、街の喧騒や騒音をも含めての考察が可能だからである。そこで本発表の目的は、散文詩と「音」というレベルで『波』を捉えること、また、そのことを特に最終章のバーナードに関する読みに響かせることにある。
理解できない歌の美しさ
ヴァージニア・ウルフ、ヘンリー・グリーンと、1930年代のロンドン
山脇学園短期大学非常勤講師 中川 千帆
ヘンリー・グリーン (1905-73) は、ヴァージニア・ウルフとは世代も作風も異なる作家である。しかし彼が1939年に発表した小説Party Going は、ロンドンという都市が作品の舞台として重要な役割をはたす、幅広い社会階層の人々を扱った群像小説であるなど、ウルフのThe Years (1937) と興味深い共通点を持つ。本発表では、ロンドンの名もなき下層階級の人々が歌をうたい、それを中・上流階級に属する主人公が意味を理解できないまま聞く、という両作品に共通する一場面をとりあげ、この〈理解できない歌〉に込められたアイロニーを、1930年代という時代背景を踏まえた上で明らかにしていく。
Virginia WoolfとJean Rhysの比較考察―母子関係を中心に
青山学院大学非常勤講師 佐竹 由帆
Jean RhysのGood Morning, Midnightをflaneur novelとして読むCarol Dell’Amicoは、Sashaが繰り返す醜態を、規格化された大量生産型の経験に記憶が植民化されるような、自動化・消費主義に対する反ファシズムの感情表白として論じている。またAfter Leaving Mr. Mackenzieを論じる際、Sashaのような自己顕示をマゾヒズム的表現としてもとらえており、マゾヒズムとJuliaの母との関連について論じている。本発表ではMrs. Dallowayをflaneur novelとしてとらえRhysと比較し、Mrs. Dallowayにおける消費、植民化、母子関係の関連について考察したい。
ユーピア/ディストピア?『オーランドー』における生殖のポリティクス
東京学芸大学非常勤講師 加藤めぐみ
新しい遺伝学、生物学、優生学が発展した大戦間の英国。産児制限が一般化し、もっと生殖機能をコントロールできるのでは、という人々の期待を科学技術の進歩が刺激し「生殖技術をめぐる言説」が広く流通した。J.B.S. Haldane, Aldus Huxleyらの科学の読み物や近未来を描いた文学テクストでは、「人工子宮による体外発生」「単性生殖」が描かれ、生殖とセクシュアリティ、ジェンダー、個人と種、親と子、人間と機械の関係に揺さぶりが掛けられた。このような文脈で、ウルフも「不老不死、両性具有のサイボーグ」=「オーランドー」を生み出したのではないか。「生殖技術」をめぐる大戦間の言説のなかで『オーランドー』を再読したい。
第26回日本ヴァージニア・ウルフ協会大会シンポジウム
感受するモダニズム――音楽・映画・シェルショック
モダニズムの「歴史化」、「一般化・原理化」と「個別化・実証」の矛盾とその克服――この高邁な問題設定は、本協会の言説編成において支配的なものとなっている。しかし、その実体はいかなるものなのだろうか?そもそも「一般化・原理化」と「個別化・実証」は二項対立として成立しうるのだろうか?「一般化・原理化」は超越的に存在する何かではなく、「個別化・実証」の禁欲的なプロセスのなかで生み出される暫定的な思い込み(assumptions)に過ぎないのではないか?以上が今回のシンポジウムの発表者が共有する問題意識である。
今回のシンポジウムの目的は、音楽や映画やシェルショックという20世紀のモダニティに特有の感覚現象を通じて、ウルフを中心とするモダニズム文学を読み直すことにある。モダニズムとテクノロジーを主題とする研究は英米では90年代後半から流行となっているが、近年その傾向はいっそう顕著なものとなっている。テクノロジーの絶え間ない革新に身をさらさざるをえない現代の高度情報化社会の原風景をわれわれはモダニズムの時代に見出そうとしているのかもしれない。
各講師の発表要旨は以下のとおりである。
音の風景と都市―
吉野亜矢子
本発表の目的は、19世紀末からのイギリスにおける音楽の隆盛を背景に、音楽(そして音)の土着性とモダニズムの関連性をみていくことである。通常、モダニズムの文学はグラモフォンのような近代機械との関連や、あるいはワーグナーのような非常に影響力の強い作曲家との関連性で読まれることが多いが、今回は特に音の土着性、及び空間作用に着目する。
ウルフの作品において音がしばしば空間を作り上げる役割を持っていることに関しては『ダロウェイ夫人』におけるロンドンの鐘の音や、『灯台へ』における波の音などを端的な例としてあげることができる。音楽ならびに、音の風景を鍵として抽象芸術ではなく表象芸術としての音楽の立ち位置を念頭に置きつつ、モダニストの都市を読んでみたい。
視覚化への欲望――モダニズム、映画、モダニティ
佐藤 元状
本発表の目的は、モダニズムと映画の相関関係を「視覚化への欲望」という20世紀的観点から分析することにある。近年の領域横断的な文化研究が明らかにしたのは、モダニズムを代表する文学者と同時代の映画文化との密接な影響関係であった。ジョイスやウルフの文学作品に見られる映画的手法についての記述には枚挙に暇がない。また近年の映画史研究が明らかにしたのは、初期映画の進展において文学の物語性が果たした決定的な役割であった。初期映画の歴史は古典的あるいはポピュラーな文学作品や劇作品の翻案の歴史に他ならない。文学と映画のこのような相関関係を概観しながら、モダニティの歴史的要請である「視覚化への欲望」を浮き彫りにしていく。
本発表で取り扱うことになる文学者および詩人には、ジョイス、ロレンス、ドロシー・リチャードソン、T・S・エリオット、H・D、ガートルード・スタインが含まれるが、その中心に位置するのはウルフである。1920年台後半はイギリス映画の分水嶺となる重要な時期であるが、それはウルフの創作活動の最も充実した時期と重なり合う。ウルフのエッセイ「映画」(1926)は、20年代の映画と文学をめぐる言説の中でどのような位置を占めるのか、またその主張と彼女の文学的実践はどのような関係にあるのか――このような疑問を手がかりに、『ダロウェイ夫人』(1925)や『灯台へ』(1927)を文学と映画のクロスオーヴァーという視点から読み直す。
本発表では映画作品の分析も行う。取り上げる映画監督はアルフレッド・ヒッチコックである。1920年台後半に頭角を現したヒッチコックを抜きにして、イギリスのモダニズムと映画の相関関係について語ることは不可能であろう。ロンドンを舞台に階級の微妙な差異を前景化するふたつの作品、『下宿人』(1926)と『恐喝』(1929)は、主題的にも方法論的にもウルフの作品とインターテクストをなしている。ウルフとヒッチコックを結ぶロンドンの都市表象をモダニティの「視覚化への欲望」という観点から考察し、結論としたい。
シェルショックの影に― Septimus Arthur BennettとSeptimus Warren Smith
矢口 朱美
本発表はMrs DallowayにおけるClarissa DallowayとSeptimus Warren Smithのダブル性の背後に、実在の人物Septimus Arthur Bennettの存在をおくことで、新たな読みの可能性を提示しようとするものである。
セプティマス・ベネットは、ウルフがいわゆる「文学的モダニズムのマニフェスト」を作り上げるにあたり叩き台とした Arnold Bennettの実弟である。貧しい陶芸家であった彼は、第一次世界大戦下の経済的苦境をきりぬけるために、裕福な兄の助けを借りて、軍需工場で砲弾を生産する道を選ぶ。そこでの過酷な生活と労働を書き綴った彼の日記や手紙は、兄にインスピレーションを与え、兄の翻案を経て、戦時中の軍需工場にまつわる数多くの新聞記事へと昇華されていく。
このセプティマスをウルフが実際に知っていた可能性はいくつかあるが、いずれにせよシェルショックをめぐる言説の影に、戦時中の砲弾生産者の存在があることをウルフが意識していた可能性は非常に高いといえる。このことが『ダロウェイ夫人』におけるクラリッサとセプティマスのダブル性に与える意味について、本発表では考察をおこなう。
今回シンポジウムの各発表に副題を設定したのは、それぞれの発表の独創性を強調するためである。ソナタ形式における速度標語のようなものとご理解いただければ幸いである。