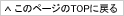2005年度
第25回大会
| 日時 | 2005年10月22日(土)9:50~17:45 |
|---|---|
| 場所 | いわき明星大学 本館四階大会議室 〒970-8551 福島県いわき市中央台飯野5-5-1 Tel: 0246-29-5111(代) Fax: 0246-29-5105 |
| 交通 | JR常磐線 上野駅~いわき駅 (特急「スーパーひたち」で約2時間10分) いわき駅バス6番のりば(いわき駅前マク ドナルド前)より約20分 |
受付 (9:30~10:00)
開会の辞(10:00)
いわき明星大学学長 高重 正明
Ⅰ 研究発表(10:00~12:10)
司会 東京学芸大学非常勤講師 加藤 めぐみ
- 出版者としてのヴァージニア・ウルフ
早稲田大学大学 院科目等履修生 内田 夕津 - 女性とファシズム ―『幕間』をめぐって
青山学院大 学大学院生 横山 勇子
司会 日本女子大学教授 三神 和子
- 子を持つこと・持たないこと ― 母という存在へのウルフのまなざし
青山学院大学非常勤講師 佐竹 由帆 - The WavesのRhodaにみるエジプト神話
東京工芸大学非常勤講師 佐藤 牧子
Ⅱ 総会 (13:00~13:20)
司会 同志社大学助教授 山本 妙
会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他
Ⅲ シンポジウム (13:30~16:15)
ベンヤミンとモダニズム作家たち ― 共同体・美学・文化
| 司会・講師 | 京都ノートルダム女子大学講師 河野 真太郎 |
| 講師 | 静岡県立大学短期大学部講師 中山 徹 お茶の水女子大学講師 三原 芳秋 |
| ディスカッサント | 帝京大学助教授 高井 宏子 |
Ⅳ 特別講演 (16:30~17:30)
司会 神戸市外国語大学教授 御輿 哲也
- Virginia Woolf in the Age of Aerial Bombardment
英国ウルフ協会Virginia Woolf Bulletin編集長 Stuart N. Clarke
閉会の辞 (17:00)
会長 都留文科大学教授 窪田 憲子
出版者としてのヴァージニア・ウルフ
早稲田大学大学院科目等履修生 内田夕津
ホガース・プレスに関する研究では、レナードの自伝がしばしば第一に重要な資料として扱われる。そのためかヴァージニアに関しては、プレスから受けた恩恵に焦点が当てられるのみで、彼女のプレスへの積極的な関わりは軽視される傾向にある。ホガース・プレスの特徴のひとつであるアンチ・ナショナリズムが論じられる際も、事情は変わらない。しかし、ナショナリズムに距離をおく姿勢は、二人の出版事業におけるヴァージニアの貢献の大きさを物語るものである。それを見過ごすわけにはいかない。本発表ではホガース・プレスの数ある「シリーズ」の一環として出版される予定であったエッセイ“Phases of Fiction”を通して、この問題を考えたい。
参考文献
- Woolf, Virginia. "Phases of Fiction," Granite and Rainbow. New York: Harcourt, Brace & World, Inc. 1958.
- Forster, E. M. Aspects of the Novel and related writings. London: Edward Arnold. 1974.
女性とファシズム -『幕間』をめぐって-
青山学院大学大学院生 横山 勇子
第二次世界大戦が勃発する前年の1938年、ヴァージニア・ウルフは最後の作品となる『幕間』の執筆を開始した。当時、ドイツやイタリアなどの独裁勢力を、他国のものとして傍観できない状況がイギリスにもあった。それは、イギリスで行われたファシストらの活動から、あるいは『幕間』以前に出版された『三ギニー』の中で、ウルフ自身がファシズムとイギリスの家父長制に類似性を見いだしている点からも明らかである。
本発表では、『三ギニー』の文脈で『幕間』を読み、『幕間』におけるファシズムについて考察する。その際、ファシズムにおいて女性が単なる犠牲者でなく、男性との共謀関係にあったという歴史の側面をふまえることとする。
参考文献
- Gottlieb, Julie V. Feminine Fascism: Women in Britain's Fascist Movement 1923-1945. (I. B. Tauris, 2000).
- Pawlowski, Merry M. Virginia Woolf and Fascism: Resisting the Dictators' Seduction. (Palgrave, 2001).
子を持つこと・持たないこと―母という存在へのウルフのまなざし
青山学院大学非常勤講師 佐竹 由帆
マギー・ハムによると、母となった姉ヴァネッサが、子どもの写真を撮ることでmatrixial gazeを再構築できたのとは異なり、ウルフは一生母の死を受け入れられず、少女時代の家族写真のモチーフを繰り返し撮ることで過去と現在をつなぎ、失った母を現在に生かし続けていた。母ジュリアのそれほどの影響力にも関わらず、母という存在はウルフの作品で肯定的にとらえられないことが少なくない。母にならなかった自分を肯定するために、母という存在の否定が必要とされたのだろうか。母という存在に対するアンビバレントなウルフの感情、子を持たず母にならない立場と作品との関係について考察してみたい。
参考文献
- Maggie Humm, Modernist Women and Visual Cultures: Virginia Woolf, Vanessa Bell, Photography and Cinema (New Brunswick: Rutgers UP, 2003).
- Virginia Woolf, To the Lighthouse, ed. Susan Dick (Oxford: Blackwell, 1992)
第25回日本ヴァージニア・ウルフ協会大会シンポジウム
ベンヤミンとモダニズム作家たち ─ 共同体・美学・文化
日本ヴァージニア・ウルフ協会では、ここ数年の大会シンポジウムや学会誌特集において、「モダニズム」を見直す作業を行ってきました。その作業の一つのキーワードとは、「歴史化」というもので、これは実証主義的・個別的にモダニズム文学を再文脈化するということにとどまらず、ウルフを代表とする「モダニズム文学」と呼ばれる文学の潮流がどのような歴史的必然性によって生まれたのか、ということを原理的・一般的に歴史化するということをも意味しました。つまり、「個別化・実証」という方向の歴史化と、「一般化・原理化」のそれの両面において、本協会はかなりの成果を挙げてきています。また、現在本協会による研究書の出版計画が進められていますが、これも上記のような流れの延長線上の企画として構想されつつあります。
今回のシンポジウムは以上のような流れを受け、ウルフという作家をその時代との関連で歴史化 ─ 「実証的」と「原理的」という、場合によっては矛盾する二つの方向を止揚したかたちで ─ するために、いわゆる「モダニズム作家」とされる他の作家と「対決」させることを試みます。その際、問題を単に文学史上の影響関係といったことにとどめず、あの時代の「何が問題だったのか」ということを浮き彫りにする狙いで、ウルフと他のモダニズム作家をつなぐ「インターフェイス」を設定しました。その名は、ヴァルター・ベンヤミン。ベンヤミンは異なる言語的・地理的・思想的コンテクストにありながら、「近代」がその極限に達したと言って良い20世紀初頭という時代の核心である諸問題に迫った批評家・思想家であり、今回対象となる作家達と真の意味で同時代人であるといえます。
さて、その「諸問題」とは具体的に何か、という点については、各講師の発表概要をご参照ください。それぞれ違う作家、作品を参照しつつ、シンポジウム副題にある、1920年代から30年代における「共同体・美学・文化」の問題を論じる予定です。
私河野は、司会の役をつとめつつ、ウルフの後期作品、特に生前未発表のエッセイ“Anon”と“The Reader”を、ベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』におけるシンボル/アレゴリー論、『ドイツ・ロマン主義における批評の概念』、そしてそのイーグルトン(『ヴァルター・ベンヤミン』)による読解を参照しつつ精読します。近年盛んに議論されている、「ウルフと共同体」という問題を、ロマン派以来の共同体論およびそれと絡み合うかたちでの文化論(レイモンド・ウィリアムズの『文化と社会』も重要なテクストです)の伝統の上に位置づけ直して再考します。
中山さんはロジャー・フライ(“Some Questions in Aesthetics,” “An Essay in Aesthetics”)とT. E. ヒューム(“Romanticism and Classicism”)の美学言説をベンヤミンの「複製技術時代の芸術作品」とともに読みます。ベンヤミンはこのエッセイで、ファシズムの目的に奉仕しない、従来の芸術理論の概念とは異なる諸概念を導入すると述べていますが、フライとヒュームはベンヤミンの言う「従来の諸概念」(contemplation, attention)に基づく美学を構築しており、「新しい諸概念」(shock, distraction)を抑圧しています。それを確認した上でウルフのエッセイ“The Cinema”やジョイスの『ユリシーズ』を再解釈します。
三原さんは、1920年代ヨーロッパの秩序の歴史的大変動、新しい世界秩序への移行が「モダニズム文学」にどのように「反映」されているのかという大きな問題にアプローチするために、T. S. エリオットとベンヤミンという二人の同時代人を「秩序」「暴力」「神話」をキーワードに精読します。エリオットからは“Ulysses, Order, and Myth”にいたる1920年前後の評論と『荒地』、ベンヤミンからは「運命と性格」「暴力批判論」「翻訳者の使命」「『親和力』論」『ドイツ悲劇の根源』など、やはり1920年前後のテクスト群に焦点をしぼり、「『神話的法秩序』がある種の『暴力』によって革命的解放につながるかもしれない、という一種のユートピア的思考がいまだに可能であった数年間」について考察します。
最後に、本協会から高井宏子さんに、講師の報告をまとめ、それを新たな「問題」として投げ返すディスカッサントとなっていただきます。
以上、講師の関心は、それぞれ「ロマン派的有機体論」、「ファシズム」、「法秩序と暴力」とアプローチは異なるものの、いずれも共同体とその美学、そして文化という点に集中しています。「モダニズム作家」という枠に分類されながらもこれほど異質な作家たちが、どのような共通の問題に対峙していたのか、これが「ベンヤミンで串刺しにする」ことによって浮かび上がってくれば、ウルフをより歴史的かつアクチュアルに読むための視界が開けるのではないかと期待しています。